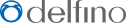-

インフルエンザ2018 ~流行状況と対策~
あたたかい気温が続いた2018年冬の始まりでしたが、12月に入ってぐんっと本格的な寒さが到来。こんなときこそ、体調管理に気を付けたいものです。さて、感染症の中で特に注意したいのはやはり「インフルエンザ」。インフルエンザが恐ろしいのは、 ・非常に高い感染力・ときに重い症状(異常行動などを含む)・深刻な合併症を引き起こすリスク といった特徴があるから。そこで、今回は、2018年のインフルエンザの傾向や流行状況、予防接種などについてお伝えしていきます。 インフルエンザの流行状況は? 国立感染研究所の『感染症発生動向調査 』による2018年第48週(11月26日~12月2日)、第49週(12月3日~12月9日)、第50週(12月10日~12月16日)を比較してみると、一医療機関当たりのインフルエンザ患者数は、0.93人(第48週)→1.70人(第49週)→3.35(第50週)と急増しており、日本は全国的にインフルエンザ流行期に突入したと言えるでしょう。以下の表は、インフルエンザの流行度合の示しています。その基準は、医療機関1件当たりの1週間の患者数が、 ・ 1人以上 … 流行開始・10人以上…「注意報」レベル・30人以上…「警報」レベル となっています。皆さんの地域ではいかがでしょうか。 しかし、その程度は都道府県ごとで異なりますので、今後もその推移を見守っていく必要があります。各地域の最新の流行状況はこちらをご参照ください。 国立感染症研究所 インフルエンザ流行レベルマップ 今年のインフルエンザの特徴 インフルエンザの原因となるウイルスは、A型、B型、C型といった3種類に大きく分類されますが、ヒトで問題となるのはA型とB型です。さらに細かく分類すると、膜表面の抗原性の組合せによって、 A型:144通り(HA16種類×NA9種類)B型:1通り(HA1種類×NA1種類) といった亜型が存在し得ます。現在は、A型ではH1亜型とH3亜型の2種類が流行しています。2018年10月29日~12月2日時点では、下記の亜型が多く検出されています。 1位:AH1pdm09(2009年に流行したA型)2位:AH3亜型(香港型と呼ばれるA型)3位:B型 これらに対するワクチンの中身は、毎年、南半球での流行状況や過去のデータを元に当年流行する亜型を予測して決定されます。今シーズンの予測は的中していたのでしょうか。 今シーズンの予防接種の効果は期待できるか 今年のインフルエンザワクチンの中身は、下記の4種類。 (1)A/Singapore(シンガポール)/GP1908/2015(IVR-180)(H1N1)pdm09(2)A/Singapore(シンガポール)/INFIMH-16-0019/2016(IVR-186)(H3N2)(3)B/Phuket(プーケット)/3073/2013(山形系統)(4)B/Maryland(メリーランド)/15/2016(NYMC BX-69A)(ビクトリア系統) これらのワクチンは、48週目までに多く検出された型に、対応できていたのでしょうか。1位~3位のウイルスに対する効果を調べてみると、以下の結果に。 1位の「AH1pdm09」に対するワクチン…(1) 2位の「AH3亜型」に対するワクチン…(2) 3位の「B型」に対するワクチン…(3)(4) きちんと対応できていたことが分かります、ただし、予防接種をしていても万全ではありません。A型は次々と変異を繰り返す性質があるため、抗体をつけたとしても、その変異に追いつけず発病してしまう可能性があります。とはいえ、予防接種に意味がないわけではありません。日本臨床内科医会が毎年行っている調査では、予防接種を受けた人の方が発病しにくいという結果が出ています。また、厚生労働省 の発表では、 *65歳以上の高齢者がワクチンを接種した場合、発病を約34~55%予防し、死亡を82%予防*6歳未満の幼児がワクチンを接種した場合、発病を約60%予防 という研究結果が出たとされています。特にB型は突然変異をせず、抗体がよく働き、発病しても重症化を防ぐことができるので、予防接種の効果は高いといえます。また、予防接種を受ける時期は、11月~12月上旬までが推奨されている理由は、 日本のインフルエンザが12月~3月に流行し、予防接種後、効果が出るまでに「約2~3週間」、効果の持続が「約5ヵ月間」と考えられているため です。流行時期から逆算しても、今からでも遅くはありません。1月上旬までに予防接種をすれば、流行最大時に間に合う計算になります。また、一度インフルエンザにかかっても、別の型に再感染する可能性も。今からでも予防接種を受けておくことをオススメします。 予防接種以外の予防法は 予防接種以外にも、下記のことに気を付けましょう。 ・人込みを避ける・外出時にマスクを着用する・加湿器などを使用して、湿度を50~60%に保つ・十分な睡眠とバランスのよい食事を心がける・うがい、手洗いをよく行う インフルエンザの感染経路は「飛沫感染」と「接触感染」と言われていますが、一部では「飛沫核感染(空気感染)」も起こっているようです。飛沫感染は、主に、患者の咳やくしゃみと一緒に放出されたウイルスを、のどや鼻から吸い込むことで感染します。そのため、流行時は人込みを避け、マスクを着用することが大切です。また、乾燥すると鼻や喉の防御機能が低下するため加湿器などで湿度を50~60%に保つことも大切。マスクは口元の湿度を保つ上でも効果的といえそうです。接触感染は、患者から飛び散ったウイルスが、物などを介して口から取り込まれることで、うがいや手洗いは基本中の基本。そして、どんな感染症でも基本となるのは、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、日頃から免疫力を高めておくこと。免疫力を高める栄養源としては、 ・免疫の働きを助ける善玉菌を多く含む食品・善玉菌の餌となる食物繊維・免疫細胞の素となるたんぱく質 といったものがオススメです。 インフルエンザにかかってしまったら インフルエンザにかかると、急速に38℃以上の高熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛といった症状が現れます。この時期は、発熱したらまずインフルエンザを疑い、発熱後12時間以上、48時間以内に医療機関で受診 するようにしましょう(※発熱後12時間以上経過しなければ、インフルエンザの検査で的確な結果が得られません。また、発熱後48時間以内に薬を服用した方が、より効果が期待できるとされています)。インフルエンザは、健康な若い人であれば自然治癒するものですが、早期回復、重症化予防、感染拡大の防止のためには、抗インフルエンザ薬の服用が望ましいとされています。しかし、代表的な薬である「タミフル」による異常行動のニュースをご存じのかたは、不安を覚える方もいるかもしれません。実際に、最近までタミフルは、10代への使用が制限されていました。しかし、2018年5月には、その使用制限が解除されています。その理由は、 薬の服用の有無や、薬の種類に関わらず、インフルエンザ感染時は、異常行動を起こす可能性がある ためだとされています。いずれにせよ、インフルエンザ患者の看病時は容体を注意深く観察する必要があるということです。既に、インフルエンザの流行は各地で開始しています。しっかりと予防対策を行っていきましょう。 (監修:防衛医科大学校 防衛医学研究センター 広域感染症学・制御研究部門 加來浩器先生) 参照URL NIID 国立感染症研究所 インフルエンザワクチン株IDSC 国立感染症研究所 感染症情報センター厚生労働省 インフルエンザQ&Aインフルエンザ過去10年間との比較グラフインフルエンザ流行レベルマップインフルエンザ罹患に伴う異常行動研究
記事を読む
-

忘れられかけた病気「結核」と「赤痢」にご用心。
「結核」、「赤痢」とは 「結核」や「赤痢」の病名を聴いたとき、皆さんはどんなことを想像するでしょうか。 不治の病を患った主人公の代表的な病名 美人が患いそうな病気 昔は死者が出たらしいけど、現代では大丈夫 そんなイメージを抱くかたも多いかもしれません。実際、結核と赤痢は、明治以降に国内に蔓延し、多くの死者を出した感染症です。それが戦後になって、環境衛生の大きな改善などによって患者数が激減しました。このことから現代では昔の病気と思われがち。しかし、現代でもこれらの感染症には注意が必要なのです。日本は人口10万人当たりの患者数が16.1人(2015年データ)と高く、「中蔓延国」に分類されています。先進国の多くは人口10万人当たりの患者数が10人以下の「低蔓延国」に分類されるなか、日本は比較的患者数が多いのです。 2018年の感染報告 2018年にも、集団感染が報告されています。 ■結核の感染事例2018年10月24日東京大田区の総合病院で結核の集団感染が発生。計24人が感染し10人が発病。60代の患者2人が死亡。感染原は、肺結核で入院し死亡した男性。2018年11月12日日本医科大学附属病院の患者11人が感染。発病者は現在なし。感染源は肺結核を発病した医師。 ■赤痢の感染事例2018年10月15日山梨県身延町の15施設で食事をした男女98人が発病。現在、全員回復。感染源は、業者が施設に納入した惣菜。2018年10月23日東京都目黒区の認可保育所の園児ら21人が感染。20人が発病し園児2人が入院。症状は軽症。感染源は不明。 このように、結核と赤痢は決して昔の病気ではありません。現在でも感染する可能性があることを念頭に、それぞれの病気について理解を深めていきましょう。 結核について整理する 結核の患者数と死亡者数は、『感染症発生動向調査』や『人口動態統計』を参照すると、以下の記録がありました。 患者数 :24,669人死亡者数:1,892人(平成28年度の数値) 現在でも、年間2000人近くの死者を出している感染症なのです。 現在でも「結核」に感染する理由 その理由は、主に以下の3つのケースが挙げられます。 ケース① 海外で感染した人が、国内で発症する 結核は、現在も世界の10大死因のひとつです。WHOの発表によると、平成28年度の結核患者数は世界で1,040万人。死亡者数は170万人に達したとあります。死亡者数の95%以上は発展途上国に偏っており、インド、インドネシア、中国、フィリピン、パキスタン、ナイジェリア、南アフリカ共和国の7ヵ国で64%を占めています。これらの国に渡航し感染した人が国内で発病し、感染拡大する恐れ可能性があります。 ケース② 第二次世界大戦前後に感染した人が、加齢とともに発病する 結核を発病する患者の70%が60歳以上。この層の多くは、第二次世界大戦前後に感染。感染した人の10~15%は1~2年のうちに発症、85~90%は、免疫により菌が休眠状態となり、一生発病しない人もいます。しかし、休眠状態になっても10~15%の人は、免疫力の低下とともに発病すると言われます。 ケース③ 予防接種(BCG)の効果は10~15年。以降は抗体を持たない状態になる 現在、乳児(生後1歳未満)にはBCGの接種が推奨されています。これにより、感染しても52~74%の確率で発症を防ぐことができます。しかし、その効果が続くのは10~15年!成人後にBCGを再接種しても効果は認められず、抗体がない状態となり感染リスクが高まります。 ■結核の症状主症状:長引く咳、痰、微熱その他:体重減少、食欲減退、寝汗重症時:倦怠感、息切れ、血の混じった痰、喀血(血を吐くこと)、呼吸困難 ■結核の感染経路と予防法感染経路:患者の咳やくしゃみを吸い込む「飛沫核感染」予防法 :適度な運動、十分な睡眠、バランスの良い食事、早期発見 結核の重症化を防ぐためには早期発見が重要。2週間以上の咳や痰が続く場合は医療機関で受診し、ご自身の重症化、周囲の感染拡大を防ぎましょう。 赤痢について整理する 次に、赤痢について整理していきます。赤痢には、以下の2種類があります。 細菌が病原となる「細菌性赤痢」 原虫が病原となる「アメーバ性赤痢」 細菌も原虫も目に見えない微生物ですが、細胞形態、大きさや遺伝子数などに違いがあり、主に2種類の赤痢が存在します。赤痢の患者数は、『感染症発生動向調査』によると、以下の記録がありました。 細菌性赤痢 : 121人アメーバ性赤痢 :1,151人(平成28年度の「赤痢」患者数) 同年度における死亡者数データは確認できませんでしたが、国立感染研究所の報告によると、1999年4月~2006年12月でアメーバ性赤痢に感染した4,129人のうち、27人が死亡とありました。 現在でも赤痢に感染する理由 赤痢に感染する主な理由は、以下の2つ。 理由① 発展途上国で蔓延、渡航者が感染し国内で発病する赤痢の患者数が多い国 は、スーダン、インド、アルゼンチン、メキシコ、イラン、サウジアラビア、中国、バングラデシュ。年間、数十万人の患者数と推定されています。これらの国に渡航し感染した人が国内で発病し、感染が広がるケースがあります。 理由② アメーバ性赤痢の患者数が増えている米国では、男性同性愛者間での「アメーバ性赤痢」の存在が認められていました。一方、日本では、赤痢というと「細菌性赤痢」を指すのが一般的でしたが、日本国内でもアメーバ性赤痢が1980年頃から少しずつ増加。2003年以降は「細菌性赤痢」の報告患者数を超え、現在では約10倍の患者数となっています。感染報告数が多いのは、下記のような事例。 ・男性同性愛者の感染事例・発展途上国からの帰国者の感染事例・知的障害者施設での感染事例 男女比は、「男性:女性=8:1」と、男性が圧倒的に多いのが特徴です。 ■赤痢の症状 細菌性赤痢の症状主症状:全身の倦怠感、悪寒を伴う急激な発熱、水様性の下痢、腹痛、しぶり腹(便意があるのに出ない)、膿粘血便(※近年、重症例はあまり報告されていません) アメーバ性赤痢の症状主症状:下痢、粘血便(イチゴゼリー状)、しぶり腹(便意があるのに出ない)、排便時の下腹部痛や不快感重症時:38~40℃の熱、右のわき腹の痛み、肝臓のはれ、吐き気、嘔吐、体重減少、寝汗、全身の倦怠感 ■赤痢の感染経路と予防法 細菌性赤痢の場合感染経路:保菌者の糞便や、それらに汚染された手指、食品、水、ハエ、器物などを介した「経口感染」予防法 :手洗い、うがい、患者の多い国で、生もの、生水、氷などを飲食しない アメーバ性赤痢の場合感染経路:感染した人の排泄物や性行為を介しての「経口感染」予防法 :手洗い、うがい、患者数の多い国で生もの、生水、氷などを飲食しない、性交渉時での注意 結核も赤痢も、死に至る可能性のある恐ろしい感染症ですが、日頃から高い免疫力を保持していれば感染しても発病しにくいため、規則正しい生活が大切です。身体の不調を感じたときは、単なる風邪と決めつけず早めの受診を心がけましょう。 「delfino施設まるごと抗菌」とは 感染症対策製品「delfino(デルフィーノ)」は、「感染ゼロをめざして」というコンセプトのもと、光触媒(酸化チタン)、抗菌触媒(銀)、三元触媒(プラチナ)などの触媒を組み合わせることで、それぞれの触媒反応が持つ効果を相乗的に発揮させながら、それぞれの弱点を補うという発想の抗ウイルス・抗菌・防臭剤です。専用噴霧器によって、デルフィーノをμ(ミクロン)単位の粒子で噴霧、密閉空間に充満させていくことで、壁面だけでなく、カウンター、チェア、デスク、キャビネットなどのあらゆるものを抗ウイルス・抗菌コーティングして、施設内での感染リスクを軽減します。お問い合わせは以下のリンクから。 お問い合わせ
記事を読む