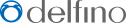
2024.02.14お知らせ新商品
オフィスや商業施設などの防災対策に。火災避難用タオル「救煙くん」の取扱いを開始
感染症対策製品「delfino」を展開する株式会社デルフィーノケア(東京都目黒区/代表取締役 宮本貴司、以下「当社」)は、火災避難用タオル「救煙くん」の取扱いを開始致しました。 ■火災避難用タオル「救煙くん」火災発生時に有毒ガスから命を守るためには、二酸化炭素を取り除いて5分以上、酸素を供給しなければなりません。火災避難用タオル「救煙くん」は、必要な酸素を15分間供給し、安全に避難することができます。 ■「救煙くん」の特徴火災時に『救煙くん』は3つの特長で大切な命を守ります。【1】酸素発生装置を内蔵! ・NASAの宇宙飛行士が使用する呼吸装置を応用 ・15分間呼吸を確保【2】5層フィルター構造! ・KF94認証のフィルター生地を使用・活性炭フィルター生地で有毒ガスを遮断【3】保管&利用時の利便性 ・誰でも簡単、2~3秒で使用 ・3年半の保存が可能で備蓄向き「救煙くん」は、一般社団法人防災安全協会が認証する防災製品等推奨品マーク「防災認証」」を取得しています。詳細は弊社窓口までお問合せください。お問い合わせ窓口平日10:00~18:00■デルフィーノケアの事業について 当社は、「感染ゼロ」をめざし、安心・安全・長期間持続の抗ウイルス・抗菌対策製品「delfino(デルフィーノ)」を主力製品として、20年以上にわたって事業展開しております。「delfino」は、安心・安全な感染症防御策のひとつとして法医学の医療現場で生まれました。手洗い・マスク、三密の回避などの感染症対策は重要ですが、個人の良識・道徳観に依存するため万全な対策とは言えません。しかし、空間内のあらゆる部位を抗菌コーティングする「delfino」なら、より高いレベルで安心・安全な環境を実現することができます。■会社概要:株式会社デルフィーノケア商 号:株式会社デルフィーノケア代表者:代表取締役 宮本 貴司所在地:東京都目黒区中目黒2-6-24-1F 今後ともご愛顧いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2023.08.31お知らせ新商品
【Del repro-C】今注目されています。捨てるより再利用する選択
感染ゼロをめざして、感染症対策製品「delfino」を展開する株式会社デルフィーノケア(東京都目黒区/代表取締役 宮本貴司、以下「当社」)は、オフィスチェア全般の「クリーニング+抗菌」サービスを実施いたします。 Del repro-Cとは Del repro-Cは、オフィスチェア全般の椅子をDFC(ドライフォームクリーニング)施工を行った後にデルフィーノの抗菌コーティングを付加し、見た目も綺麗に、安心・安全にご使用していただける椅子を実現いたします。 ■SDGsの実現 ■ドライフォームクリーニング 大量の空気を含んだ細かい泡の力で浮かした汚れを泡に包み込み洗浄する工法です。ドライフォームは水分含有量7%の泡を使用し、洗浄後の椅子は半日程度で乾燥し翌日には使用可能(気温、湿度により乾燥時間は異なります)となるのも一つの特徴です。 ■クリーニング例 ■クリーニングの手順 ■料金
2023.04.21CSR
MBT難病克服キャンペーン協賛のお知らせ
感染ゼロをめざして、感染症対策製品「delfino」を展開する株式会社デルフィーノケア(東京都目黒区/代表取締役 宮本貴司、以下「当社」)は、一般社団法人MBTコンソーシアム(奈良県橿原市/理事長 細井裕司、以下「MBTコンソーシアム」)の推進している「MBT難病克服キャンペーン」に協賛しました。 MBT難病克服キャンペーンとは MBT(Medicine-Based Town, 医学を基礎とするまちづくり)は、「住居医学」と「MBE」の体系の統合であり、超高齢社会に対応したまちづくりを行と共に、新産業創生と、地方創生を行うことを目的としています。一般社団法人MBTコンソーシアムは、難病に関わる研究者や、難病に携わる人々や組織を支援する「MBT難病克服支援キャンペーン」を推進しています。 ■ 協賛の背景 当社では設立以来、社会貢献事業の一環として、2011年の東日本大震災での衛生環境整備支援や、障害児保育園への「施設まるごと抗菌」の提供、小学校での手洗い教室の実施などを国内各所で行なってきました。今回、MBTコンソーシアムによる難病支援事業に賛同し、協賛させていただくことになりました。 デルフィーノケアの事業について 当社は、「感染ゼロ」をめざし、安心・安全・長期間持続の抗ウイルス・抗菌対策製品「delfino(デルフィーノ)」を主力製品として、20年以上にわたって事業展開しております。「delfino」は、安心・安全な感染症防御策のひとつとして法医学の医療現場で生まれました。手洗い・マスク、三密の回避などの感染症対策は重要ですが、個人の良識・道徳観に依存するため万全な対策とは言えません。しかし、空間内のあらゆる部位を抗菌コーティングする「delfino」なら、より高いレベルで安心・安全な環境を実現することができます。 ■組織概要:一般社団法人MBTコンソーシアム組織名:一般社団法人MBTコンソーシアム代表者:理事長 細井裕司所在地:奈良県橿原市四条町840番地 ■会社概要:株式会社デルフィーノケア商 号:株式会社デルフィーノケア代表者:代表取締役 宮本 貴司所在地:東京都目黒区中目黒2-6-24-1F 今後ともご愛顧いただけますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2023.03.24CSR
南紀白浜空港内にてMA-T™マウスウォッシュの無料配布を実施
株式会社デルフィーノケア(東京都目黒区、代表取締役:宮本貴司。以下「当社」)は、2023年3月27日から31日までの期間、和歌山の空の玄関口である南紀白浜空港内にて、紀南に来訪される皆様が安心・安全にご当地で過ごしていただく取組の一環として、「MA-T™マウスウォッシュ」の無料配布を実施いたします。 南紀白浜エアポートおよび当社は、2020年6月より、誰もが安心・安全に和歌山県を訪れ、心豊かに過ごせる地域づくりの施策のひとつとして「和歌山まるごと抗ウイルス大作戦*」を掲げ、これまで和歌山県内観光施設や生活施設など約50施設の衛生環境づくりに取り組んでまいりました。その取り組みの一環として、2023年3月27から31日までの期間、南紀白浜空港内にて当社が会員となっている「一般社団法人日本MA-T™工業会**」の協力のもと「MA-T™マウスウォッシュ(ポーションタイプ)」の無料配布提供を実施いたします。今回のイベントに関わる空港スタッフもMA-T™マウスウォッシュを使用して感染対策に取り組んでいます。* 和歌山まるごと抗ウイルス大作戦 2020年6月より感染症の予防対策が中長期で求められる新しい日常に向けて、地域全体の安全・安心を守り、地域住民や地元事業者が安心して日常生活や事業活動の継続ができ、また観光・ビジネスの旅行者にも安心して選ばれる持続可能な地域づくりを目指す地域連携プロジェクト。**一般社団法人日本MA-T工業会 日本で発明された酸化制御技術であるMA-T™(Matching transformation system)の価値向上と普及を目的とし、オープンイノベーションのプラットフォームとして、2020年11月に設立された団体(東京都千代田区、代表理事:川端克宜 [アース製薬株式会社 代表取締役社長])。会員企業は100社(2022年12月末現在)で、「感染制御」「医療・ライフサイエンス」「食品衛生」「農業・林業」「表面酸化」「エネルギー」の6つの分野で事業活動している。 ■MA-Tマウスウォッシュについて MA-T™認証マーク MA-T™は、必要な時に、必要な量の活性種(水性ラジカル)を生成させることで、流行性ウイルスをはじめとするウイルスの不活化、種々の菌(細菌)の除菌を可能にする注目の最新技術で、要時生成型亜塩素酸イオン水溶液と称します。特に口腔ケアは感染対策としての重要性が認識されており、MA-T™マウスウォッシュが活用されています。MA-T™を採用した製品(MA-T™認証マークの表記あり)は、プロ野球、Jリーグ、大相撲、劇団、オペラなどのスポーツやエンターテインメントをはじめ、大学病院、歯科医院、介護施設、保育園・幼稚園、自治体、ホテル、飲食店などで広く採用されています。 MA-T™マウスウォッシュ(ポーションタイプ)は、ノンアルコール、香料無添加、無味のため水感覚で使用できる刺激のない洗口液で、持ち運びに便利な口腔ケア製品です。ご年齢を問わず安心して使用することができます。 今後も感染ゼロを目指し、社会に還元する取り組みを継続してまいります。引き続きご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
2023.03.03CSR
「施設まるごと抗菌・抗ウイルス」を通して誰もが安心・安全で心豊かに過ごせる場所の実現に向けて
株式会社南紀白浜エアポート(和歌山県西牟婁郡、代表取締役社長:岡田信一郎。以下「南紀白浜エアポート」)および株式会社デルフィーノケア(東京都目黒区、代表取締役:宮本貴司。以下「デルフィーノケア」)は、2023年1月30日、2月4日に和歌山の空の玄関口である南紀白浜空港の現ターミナルビルとこれから開業予定の新ターミナルビルに、「delfino施設まるごと抗菌・抗ウイルス」を実施いたしました。 南紀白浜エアポートおよびデルフィーノケアは、2020年6月より共同で、誰もが安心・安全に和歌山県を訪れ、心豊かに過ごせる地域づくりの施策のひとつとして「和歌山まるごと抗ウイルス大作戦*」を掲げ、これまで和歌山県内の宿泊・交通・飲食・テーマパークなどの観光施設から学校・福祉・銀行・オフィスなどの生活施設まで約50施設の衛生環境づくりに取り組んでまいりました。その取組みの一環として、2023年1月30日、2月4日に和歌山の空の玄関口である南紀白浜空港の現ターミナルビルとこれから開業予定の新ターミナルビルに、「delfino施設まるごと抗菌・抗ウイルス」を実施いたしました。地域の空の玄関口である南紀白浜空港の衛生環境がさらに向上したことにより、日頃から観光・ビジネスで和歌山を訪れる方々や、空港を使って県外へ出られる地域住民の方々など、空港を利用される皆さまが安心・安全に旅行や滞在をしていただける地域づくりを通じて地域の活性化に取り組んでまいります。 なお、こちらの南紀白浜空港の抗菌・抗ウイルス施工の様子は、テレビ朝日系テレビ番組「朝メシまで。」(関東地域では、3月4日(土)24時30分放映)にて放映されました。 * 和歌山まるごと抗ウイルス大作戦2020年6月より感染症の予防対策が中長期で求められる新しい日常に向けて、地域全体の安全・安心を守り、地域住民や地元事業者が安心して日常生活や事業活動の継続ができ、また観光・ビジネスの旅行者にも安心して選ばれる持続可能な地域づくりを目指す地域連携プロジェクト。 「delfino施設まるごと抗菌・抗ウイルス」採用の背景 首都圏とつながる空の玄関口である南紀白浜空港では、空港利用者の皆様にさらに安心して施設をご利用いただけるように、これまでの空港職員のマスク着用やアルコール消毒液の設置、空港利用者の三密回避などの感染症予防対策を行ってまいりました。しかし、空港利用者への任意での協力依頼や空港職員による人海戦術での対策には限界があり、全てのお客様に対して「常時・強制的にリスク低減ができる感染症予防対策」を必要としていました。デルフィーノは施設全体をくまなく抗菌・抗ウイルスできるだけでなく、産学連携で医療現場でも採用されいる独自技術を活用し、第三者専門機関による複数の効果エビデンスも有しているため、最も信頼性の高いサービスであると考えて採用にいたりました。また、SIAA(抗菌製品技術協議会)の厳しい人体安全性基準をクリアしており、施設の防カビ・防臭等の衛生サービスの向上にも寄与するため、高い安全性とおもてなしの観点からも導入を決定しています。 株式会社南紀白浜エアポートについて 南紀白浜空港の民営化にともない、2018年に設立された民間資本100%の空港運営会社。「空港の発展は地域の発展から」をコンセプトに、誘客と地域活性化の専門部署を設けて、観光・インバウンドから企業誘致・ワーケーションまで幅広く地域課題解決型の事業を展開。和歌山県南部の12市町村を広域でマネジメント・マーケティングする観光庁認定「紀伊半島地域連携DMO」として、着地型旅行事業(紀伊トラベル)などを通じた持続可能で稼げる地域づくりを実践している。
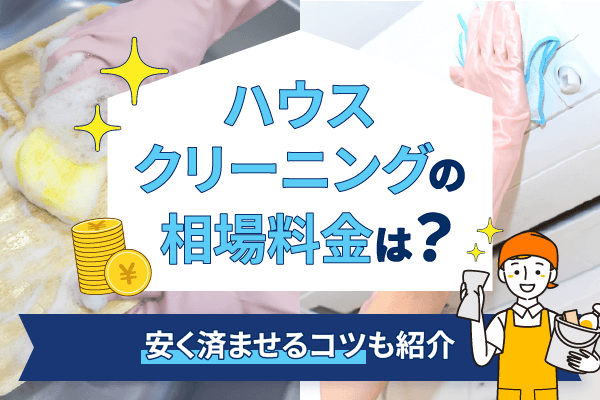
2025.10.06コラム
ハウスクリーニングの料金相場は?安く済ませるコツも紹介
「ハウスクリーニングの相場ってどのくらい?」と気になる方も多いと思います。 水回りクリーニングセット料金相場比較表 結論、ハウスクリーニングの相場は間取りや汚れ具合・業者によって大きく変わります。 以下は「間取り別」「場所別」の相場をまとめましてので参考にしてみてください。 間取り別 1R〜2DK(マンション) 約24,000~54,000円 2LDK〜3DK(戸建含む) 約35,000~87,000円 3LDK〜4DK(戸建含む) 約48,000~95,000円 場所別 エアコン(壁掛けタイプ) 約9,000~13,000円 水回りセット(2〜4点) 約30,000~58,000円 1R・1Kなどの単身向けなら2〜5万円前後で依頼できるケースが多い一方、3LDK以上や戸建てになると8万円を超えることも珍しくありません。 さらに、同じ間取りでも「空室か入居中か」「水回りの汚れがどれくらいか」「ペットや喫煙の有無」などによって追加料金が発生する可能性もあります。 以下に、ハウスクリーニングの費用を安く抑える方法をまとめました。 4つの実践テクニック 複数箇所をまとめて依頼して「セット割」を活用する オフシーズン(閑散期)を狙えば料金が下がる傾向に 掃除しやすい環境に整えておくことで追加料金を防ぐ 必ず複数社から無料見積もりを取り比較するのが鉄則 ハウスクリーニングでは、依頼前に相場感を把握し作業内容が明確な業者を比較して選ぶことがとても重要です。 ハウスクリーニング業者を選ぶ際は以下のポイントを確認してみてください。 選び方の3つ 料金と作業範囲が明確に提示されているか確認➡不明瞭な表記だと追加費用がかかるケースあり 損害賠償保険・保証制度の有無を確認➡設備破損などトラブル時の補償体制は安心材料に 口コミ・評判で利用者のリアルな声を確認する➡Google Map口コミやマッチングサイトで利用者のリアルな声が重要 相場を知ったうえで「自宅の状況に合った適正価格かどうか」を見極めることが重要です。 本記事では実際に清掃内容や料金を左右する要素について詳しく解説していきます。 この記事からわかること ハウスクリーニングの相場費用 ハウスクリーニングを相場より安く抑える方法 ハウスクリーニング業者の選び方 株式会社デルフィーノケアについて 株式会社デルフィーノケアでは、独自の抗ウイルス・抗菌剤「デルフィーノ」を用いて、医療・教育・オフィスなど多様な現場の衛生環境を改善する企業です。 お問い合わせはこちら▶ 法医解剖や感染現場で培った技術を活かし、抗菌・防臭・防カビ施工を全国で展開しています。 詳細な事例はこちら▶ 当記事では上記の知見を活かし安心・安全な環境づくりの一環としてハウスクリーニングに関する情報をご紹介しています。 ハウスクリーニングの料金相場は居住状況で変動する ハウスクリーニングとは、専門業者が住宅内の汚れやカビ・ホコリなどを専用の洗剤や機材を使って徹底的に清掃するサービスのことを指します。 ハウスクリーニングの料金相場は、居住状況によって大きく変動します。 特に「空室」と「入居中」とでは、同じ間取りであっても作業内容や時間が異なるため、料金にも差が生じやすくなります。 以下は主な料金が変動する理由をまとめましてので参考にしてみてください。 料金が変動する理由 作業範囲・作業時間➡清掃の対象範囲や依頼箇所が多いほど、作業工数が増えるため費用も上がります。 汚れの度合い➡汚れの度合いが重度なほど、専用機材や時間が必要になるため料金が高くなります。 駐車スペース➡駐車場の有無や建物構造など作業環境によって、追加料金や作業負担が発生することがあります。 これら3つの要素は、同じ「3LDKの空室清掃」でも1万円以上料金差が出ることもあるほど、クリーニングの費用を左右する核心部分です。 料金表だけでは見えにくいこれらの条件を把握し、見積もり前に自宅の状況を整理しておくことが納得価格でサービスを受けるためのポイントといえるでしょう。 1R〜一戸建てまで対応!間取り別ハウスクリーニング料金相場を紹介 ハウスクリーニングの料金は、「間取り」と「住まいの状況」によって大きく変動します。 一般的には、部屋数が少なく空室であるほど安く広い一戸建てかつ入居中の状態では高くなる傾向があります。 実際の料金は「標準料金」+「追加料金」の合算で決まります。 標準料金は部屋の広さに応じて設定されていますが、追加料金は物件ごとの汚れの程度や生活状況によって発生する変動費です。 以下に、代表的な間取りごとの料金相場を「住宅タイプ」「居住状況」別にまとめました。 【間取り別・住宅タイプ別ハウスクリーニング料金相場】 間取り 一戸建て/入居中 一戸建て/空室 マンション/入居中 マンション/空室 1R~2DK ― ― 約32,000~54,000円 約24,000~44,000円 2LDK~3DK 約65,000~87,000円 約50,000~70,000円 約42,000~68,000円 約35,000~59,000円 3LDK~4DK 約70,000~95,000円 約55,000~78,000円 約55,000~87,000円 約48,000~75,000円 4LDK~5DK 約70,000~110,000円 約60,000~97,000円 ― ― 注意点 表に記載した金額は、標準料金+軽微な追加料金(汚れ対応・駐車場等)を含んだ実勢価格帯です。 実際の金額は、築年数・汚れの程度・清掃箇所の希望内容などによって変動します。 見積もり時は、業者に対し「居住状況」「設備の数」「気になる汚れの種類」などを具体的に伝えることが、適正価格を得るためのポイントです。 ハウスクリーニングの料金は、単に「間取りの広さ」だけで決まるわけではありません。 ハウスクリーニングの料金は、面積の広さだけでなく、住まいの「個別事情」によって細かく変動します。 ここからは間取り別の料金相場を詳細に説明していくので参考にしてみてください。 単身者向け(1R〜1LDK)のハウスクリーニング料金相場 1R〜1LDKにおける料金相場は約2.4万円~6万円前後です。 1R・1K・1DK・1LDK・2DKといった単身者向けの物件は、間取りがコンパクトである一方、キッチン・浴室・トイレが近接しており、汚れが集中しやすい傾向があります。 プロのハウスクリーニングを依頼する際は、単純な面積だけでなく作業のしやすさや状態も費用に影響します。 間取り 状況 標準料金(税込) 追加料金目安(税込) 総額目安(税込) 1R~2DK 空室(マンション) 約24,000~38,000円 +4,000~6,000円 約24,000~44,000円 1R~2DK 入居中(マンション) 約32,000~46,000円 +5,000~8,000円 約32,000~54,000円 追加料金の発生条件例 キッチンや浴室に長年の蓄積汚れがある 家具・家電が多く、移動や養生が必要な場合 タバコ・ペットの臭いが残っている場合 作業車を停められるスペースがなく、近隣駐車場を利用する場合 狭い部屋だからといって、必ずしも料金が安いとは限りません。 特に、単身者向け物件は換気が不十分なことも多く、水回りや壁紙にカビや汚れが目立ちやすくなる傾向があります。 また、荷物が多くスペースが限られる場合、作業効率が低下しその分コストに反映されることがあります。 こんな方におすすめ 賃貸物件の退去時に敷金を少しでも取り戻したい方 入居前にリセットされた状態で新生活を始めたい方 引っ越しのタイミングでまとめて清掃を済ませたい方 荷物を運び出した直後など、空室状態で依頼できる方 空室の状態で依頼すれば、作業効率が良くなり料金も抑えやすくなります。 特に「退去前」や「入居前」は、最もコストパフォーマンスが高くなるタイミングです。 少しでも費用を抑えたい方には、このタイミングでの依頼がおすすめです。 2LDK〜3DKの料金相場|カップルや小世帯に多い間取り 2LDK~3DKの相場は約3.5万円~7万円前後です。 2LDK~3DKの物件は、カップルや小さなお子さまのいる家庭など、少人数世帯が多く住む間取りです。 部屋数・水回りが1Rなどに比べて多くなるため、ハウスクリーニングでは作業範囲が広くなり料金も段階的に上昇します。 特に「水回り2箇所以上」「収納スペースが多い」といった構造により、清掃にかかる時間と人員も変動するため、相場感の理解が重要です。 間取り 状況 標準料金(税込) 追加料金目安(税込) 総額目安(税込) 2LDK~3DK 空室(マンション) 約35,000~52,000円 +5,000~7,000円 約35,000~59,000円 2LDK~3DK 入居中(マンション) 約42,000~58,000円 +6,000~10,000円 約42,000~68,000円 追加料金の発生条件例 油汚れやカビが強く、作業に時間がかかる 家具の量が多く、移動や養生作業が必要 ペットの毛・臭いなどが染みついている 駐車場がなく、作業車両の確保が難しい この間取りになると、エアコン2台以上、バルコニー、浴室・トイレが分離されているケースも多くなります。 それぞれに専用の作業工程が必要なため、1Rや1Kと比べてクリーニング料金は上がりやすくなります。 ただし、水回りやエアコンなどの「まとめて依頼」や、「空室時」の清掃でコストダウンを狙える場合もあります。 個別に依頼するより、セットメニューや定額プランの方が割安になるケースが多いため、複数箇所のクリーニングを検討している方は特におすすめです。 こんな方におすすめ 夫婦や小さいお子さまとの暮らしで生活感のリセットを図りたい方 引っ越しやリフォームに伴う空室状態でのクリーニングを検討している方 キッチンや浴室など、複数の水回りが気になってきた方 共働きでなかなか時間が取れず、一度リセットして家事負担を軽くしたい方 空室時であればスムーズに作業が進み、費用を抑えられる可能性も高くなります。 また、日常清掃では手が回らない場所をまとめてリセットすることで、生活の快適さが大きく変わるはずです。 3LDK〜4LDKの料金相場|ファミリー層向け物件の価格感 3LDK~4LDKの相場は、約4.8万円~8.7万円前後が目安です。 この間取りはファミリー層に最も多く、部屋数・水回り・収納スペースなどの増加によりハウスクリーニングの作業範囲が一気に広がります。 特に小さなお子さまのいる家庭では、食べこぼし・手垢・水まわりの使用頻度が高く、日常的に汚れが溜まりやすいため、プロの清掃が求められる場面も多いのが特徴です。 間取り 状況 標準料金(税込) 追加料金目安(税込) 総額目安(税込) 3LDK~4LDK 空室(マンション) 約48,000~68,000円 +6,000~10,000円 約48,000~78,000円 3LDK~4LDK 入居中(マンション) 約55,000~75,000円 +7,000~12,000円 約55,000~87,000円 追加料金が発生しやすい例 浴室・トイレが2箇所以上ある 広めのバルコニーやベランダが含まれる 収納やクローゼット内も清掃対象となる ペットを飼っている・子どもの落書きや傷が多い 駐車スペースがなく、近隣の有料駐車場を利用する場合 この規模の住宅では、各部屋や水回りの距離が広く、作業時間が長くなる傾向があります。 また、エアコンや浴室乾燥機などの設備も複数台ある場合、専門的な分解洗浄が必要となりオプション費用が加算されることもあります。 一方で、空室状態であれば作業がスムーズに進みやすく、入居中よりも料金を抑えられる可能性があります。 また、水回りやエアコンなど複数箇所を一括で依頼すると、セット割引や定額プランが適用されるケースもあるためコストパフォーマンスを高めたい方には有効です。 こんな方におすすめ 子どもやペットがいて、家全体に生活感が出やすいご家庭 年末や引っ越しを機に、住まいを一度リセットしたい方 エアコン・水回りなど、手の届きにくい場所の汚れが気になってきた方 忙しくて掃除に手が回らず、定期的に専門業者に任せたい方 広めの住宅は、そのぶん手が回らない箇所も増えがちです。 プロのハウスクリーニングを活用することで、家族全員がより快適に過ごせる空間づくりが実現できます。 一戸建て住宅のハウスクリーニング相場と注意点 一戸建て住宅のハウスクリーニング料金相場は、約6万円~10万円台前半が目安です。 マンションに比べて構造が複雑で、作業対象となる部位が多いため全体的に高めの傾向があります。 階段・玄関ポーチ・ベランダ・外まわりなど、マンションでは必要ない清掃も含まれる点が料金に影響します。 間取り 状況 標準料金(税込) 追加料金目安(税込) 総額目安(税込) 一戸建て(80㎡〜120㎡) 空室 約60,000~85,000円 +8,000~12,000円 約60,000~97,000円 一戸建て(80㎡〜120㎡) 入居中 約70,000~95,000円 +10,000~15,000円 約70,000~110,000円 追加料金が発生しやすい例 2階建て以上で階段の上下移動が多い 玄関や庭、外壁まわりの清掃を依頼する場合 駐車スペースがない、または作業車の搬入が難しい立地 納戸・ロフトなど通常よりも清掃が困難な場所がある ペットやタバコの臭いが強く、脱臭作業が必要なケース 一戸建て住宅は空間が広いぶん、掃除にかかる時間や人員が多くなる傾向にあります。 また、マンションと違って外部との境界が多いため、ベランダ・雨戸・窓ガラス・外構部分の清掃も必要になることがあります。 さらに、2階建てや3階建ての場合は、階段部分や手すりの拭き上げも加わるため、作業の工程が増える点にも留意しましょう。 一方で、空室状態での依頼であれば、作業効率が大幅に向上し費用を比較的抑えられる可能性があります。 特にリフォームや売却前後、入退去のタイミングでは、全体の清掃を一括で依頼することで仕上がりも良くなり、物件価値にもつながるメリットがあります。 こんな方におすすめ マイホーム全体を定期的にリフレッシュしたい方 リフォーム・リノベーション後に全体を清掃したい方 引っ越しや売却を控えて物件の印象を良くしたい方 高齢の家族が住む実家の清掃を依頼したいと考えている方 一戸建ては居住空間が広いだけでなく、構造や生活スタイルも多様なため、料金のブレ幅が大きいことが特徴です。 複数社に見積もりを依頼し、対象範囲やオプション内容を丁寧に確認することが納得できるハウスクリーニングへの近道といえるでしょう。 間取りだけで判断しない!料金が上下する要素にも注目 ハウスクリーニングの料金は「1LDKだから○万円」「一戸建てだから○万円」と、間取りだけで一律に決まるものではありません。 実際の費用は、住まいの状態・立地・生活スタイルなど、さまざまな要素が重なって算出されます。 ここでは、料金が上下しやすい主要な要因を整理してご紹介します。 料金に差が出る主な要素 汚れの度合い 長年放置された水アカ・油汚れ・カビなどは除去に時間がかかり、費用が上がる傾向 家具・荷物の多さ 入居中で動線が狭く、家具を移動しながらの作業が発生する場合は手間が増える ペットの有無 毛や臭いの除去に特別な機材・洗剤が必要な場合、追加料金対象になることも 作業環境 駐車場がない、高層階で搬入が困難、階段移動が多い等の条件はコストに影響 作業対象の追加 クローゼット内部、窓サッシ、雨戸、玄関アプローチなどを希望する場合、範囲外費用として加算される 同じ3LDKの間取りであっても、生活状況や住宅条件によって2万円以上差が出ることもあります。 例 状況 費用 【ケースA】 空室・築浅・家具なし 約48,000円 【ケースB】 入居中・子育て中・荷物多め 約70,000円以上 「広さが同じだから安く済むはず」と思って依頼すると、後から予想外の追加費用が発生することもあります。 納得感のある依頼をするためには、料金表だけでなく見積もり時のヒアリング内容や現地確認の有無を丁寧にチェックしておくことが重要です。 見積もり時に確認しておきたいポイントは以下3点です。 ・「標準料金に含まれていない作業」があるか事前に確認・写真や間取り図があれば、事前見積もりの精度が上がる・入居中の場合、掃除のしやすい状態に整えておくと割引の可能性も 場所別でハウスクリーニング料金相場を紹介 ハウスクリーニングでは、依頼する「場所」ごとに料金が異なります。 作業の手間や専門性、汚れの種類により、相場に幅が出やすいのが特徴です。 以下に、代表的な清掃箇所の相場料金を一覧にまとめました。 【場所別・ハウスクリーニング料金相場】 清掃箇所 相場料金(税込) エアコン(壁掛け) 約9,000~13,000円 キッチン 約9,000~15,000円 換気扇(レンジ) 約10,000~17,000円 浴室(お風呂) 約12,000~18,000円 トイレ 約7,000~11,000円 洗面所 約6,000~10,000円 ベランダ 約8,000~14,000円 水回りセット 約30,000~58,000円 ※料金は清掃範囲や汚れ具合、設備の構造により前後します。 複数箇所の依頼やオフシーズン予約で、トータル費用を抑えることも可能です。 以下では場所別の相場を詳しく説明していくので参考にしてみてください。 エアコンクリーニングの相場|壁掛けタイプ・お掃除機能付きの違いとは エアコンクリーニングの相場は、約9,000円〜20,000円前後です。 料金はエアコンの機種によって異なり、特に「お掃除機能の有無」が価格に大きな影響を与えます。 【エアコンのタイプ別クリーニング相場】 エアコンタイプ 相場 特徴 壁掛けタイプ(一般機種) 約9,000〜12,000円 分解が比較的簡単で、価格もリーズナブル お掃除機能付きタイプ 約15,000〜20,000円 構造が複雑なため、分解と洗浄に高度な技術が必要で割高 ※高所設置・設置環境・汚れの度合いによって、追加料金が発生する場合があります。 「お掃除機能付き」と聞くと、「内部までキレイに保たれる」と思いがちですが実際に自動で掃除されるのはフィルターのホコリのみが多いです。 ファン内部や熱交換器にはカビや汚れが残っていることが多く、プロによる分解洗浄が不可欠です。 そのうえ、お掃除機能付きエアコンは配線・基板・分解構造が複雑なため、作業時間が長く専門技術も必要になることから料金が高めに設定されています。 家庭内にエアコンが2台以上ある場合、2台目以降は1,000〜2,000円引きになる割引プランを用意している業者も多く見られます。 また、「防カビコート付き」「室外機セット」などのオプションプランもあり、パックで依頼することで総額が抑えられるケースもあります。 業者に依頼するメリット 内部のカビ・ホコリを徹底洗浄し、アレルギー対策にも効果的 冷暖房効率が改善し、結果的に電気代の節約にもつながる 機器寿命の延長や異音・異臭トラブルの予防につながる 専用高圧洗浄機を使った安全で確実な作業で安心感がある 市販のスプレーでは届かないエアコン内部の洗浄は、年に1回〜2年に1回を目安にプロに任せるのが理想的です。 とくに気温が上がる前の5〜6月は、予約が集中する前の依頼ベストシーズンです。 健康面と快適さの両方を保つためにも、早めの対応がおすすめです。 キッチン・換気扇まわりの清掃相場|油汚れが落ちにくい箇所ほど高くなる? キッチンクリーニングの相場は、約9,000円〜14,000円前後です。 レンジフード(換気扇)とのセットプランや、壁面・床・収納棚の拭き上げまで含めた内容になると、さらに費用が加算されることがあります。 【キッチンクリーニング料金相場(税込)】 プラン内容 料金相場 主な作業範囲 基本プラン(標準清掃) 約9,500〜11,000円 シンク・コンロ・天板・排水口まわりの洗浄 換気扇込みのパックプラン 約13,000〜16,000円 上記+レンジフードの分解洗浄・ファン洗浄など フルパック(壁・床・棚含む) 約16,000〜19,000円 キッチン全体+壁面・床・棚の拭き上げ清掃含む ※築年数や汚れの度合い、油のこびりつき具合によって追加料金が発生することがあります(+1,000〜3,000円程度が目安)。 キッチンのハウスクリーニングでは、コンロ・シンク・作業台などの表面清掃だけでなく、排水口や水栓周り、油汚れがたまりやすい壁面やレンジフードまで幅広く対応します。 業者によっては、収納棚の外側や床面の拭き上げまで含まれることもあります。 業者に依頼するメリット 市販の洗剤では落としきれない油汚れも、専用洗浄剤と高温スチームで分解除去 排水口やシンクのぬめり・ニオイも徹底洗浄、衛生面が大幅に改善される 焦げ付きやシミを除去し、清潔感のあるキッチンにリセットできる 自分で掃除しにくい換気扇や奥まった部分も丁寧に清掃してもらえる 特にキッチンは「油×湿気×熱」の条件がそろいやすく、他の場所に比べて汚れのこびりつきが強い傾向にあります。 自力では落とせない箇所も、プロに任せれば衛生的で快適な状態に整えることが可能です。 汚れを溜め込む前に、半年〜1年に一度の専門清掃を検討するとよいでしょう。 浴室(バスルーム)のクリーニング相場|カビ・水垢が多いと追加費用も? 浴室(お風呂場)のクリーニング相場は、約11,000円〜17,000円前後です。 天井・壁・床に加えて、浴槽のエプロン内部や排水口など、見えない部分まで対応するかどうかで価格が変動します。 【浴室クリーニング料金相場】 プラン内容 相場目安 主な対応範囲 基本プラン(標準清掃) 約11,000〜13,000円 浴槽・壁・床・鏡・蛇口まわり・排水口など 防カビコート付きプラン 約13,000〜15,000円 上記+カビ防止コーティング エプロン内高圧洗浄付きフルプラン 約15,000〜17,000円 上記+エプロン内分解洗浄・天井・換気カバーなども含む ※築年数が古い・黒カビが広範囲に広がっている場合は、追加費用が発生することがあります(+1,000〜3,000円程度)。 湿度の高い浴室は、カビ・水垢・皮脂汚れ・石けんカスが蓄積しやすく、見た目以上に手強い汚れが発生します。 市販の洗剤では落としきれない頑固な汚れや、エプロン内部のカビなどは専門業者による分解洗浄が必要です。 業者に依頼するメリット しつこい黒カビやヌメリを根本から除去でき、見た目も衛生面もスッキリ 鏡や蛇口の水垢もプロの技術で曇りなく仕上がる エプロン内部や換気扇カバーなど、家庭では難しい場所まで丁寧に洗浄 湿気によるカビ臭・雑菌リスクを減らし、快適なバスタイムを実現 浴室は毎日使用する場所でありながら、最も湿気と汚れが溜まりやすい空間でもあります。 放置すると健康被害(カビによるアレルギーや咳など)につながる可能性もあるため、1年に1回程度のプロ清掃で快適な環境を維持しましょう。 トイレと洗面所の相場|日常掃除では落とせない汚れの対処費用 トイレクリーニングの相場は、約6,000円〜10,000円前後です。 見た目は一見キレイでも、便器のフチ裏やタンク内など汚れや菌がたまりやすい場所が多く、家庭用洗剤では落としきれない頑固な汚れも少なくありません。 【トイレクリーニングの料金相場】 プラン内容 相場目安 主な対応範囲 基本プラン 約6,000〜7,500円 便器・フチ裏・床・壁面・タンク表面の洗浄 タンク内洗浄付きプラン 約8,000〜9,000円 上記+タンク内部やノズルまわりの分解洗浄 防汚・防カビコート付きプラン 約9,000〜10,000円 上記+防汚コーティング、ドアや棚などの周辺清掃も含む場合あり ※ペットのいる家庭や、尿石が固着している場合は+1,000円〜程度の追加費用がかかることがあります。 特に尿石・黒ずみ・水垢・カビなどは、時間が経つほど層のように蓄積し、ニオイの原因になります。 プロのハウスクリーニングでは、専用の酸性洗剤やブラシを使って細かい部分まで除去。 フチ裏・配管付近・床の目地など、家庭では見逃しがちな箇所まで対応します。 業者に依頼するメリット 尿石・カビ・黒ずみを根本から除去し、見た目もニオイもリセット 便座の裏やフチ、便器の奥など見落としがちな箇所まで徹底洗浄 防汚・抗菌加工で、汚れの再発を防止しやすくなる ニオイの元を断ち、清潔で快適な空間を維持できる トイレは毎日必ず使用する場所だからこそ、衛生面の影響が大きい空間でもあります。 見た目以上に汚れが蓄積しやすく、健康リスクや悪臭の原因にもなり得るため、半年〜1年に一度の専門清掃が理想的です。 窓・サッシ・網戸の清掃料金|掃除しにくい箇所はプロに頼むべき? 洗面所クリーニングの相場は、約6,000円〜9,000円前後です。 日々の手洗いや洗顔、身だしなみの場として使われる洗面台は、水垢・石けんカス・整髪料の残りなどが蓄積しやすい場所です。 一見キレイでも、鏡や水栓まわり、排水口には見えない汚れがこびりついていることがあります。 【洗面所クリーニングの料金相場】 プラン内容 相場目安 主な対応範囲 基本プラン 約6,000〜7,500円 洗面ボウル・蛇口・鏡・棚の表面・床の拭き上げなど 排水口内部・カビ除去プラン 約7,500〜9,000円 上記+排水口奥の清掃・カビや黒ずみの徹底洗浄 水回り2点セット(例:洗面+トイレ) 約12,000〜14,000円 洗面所と他1ヶ所の同時依頼でセット割引が適用される場合あり ※排水口の臭いやカビが強い場合、+1,000〜2,000円程度の追加料金がかかることがあります。 水の飛び散りや湿気が多く、鏡のウロコ状の汚れ、水栓周りのくすみ、排水口のヌメリなど、気づきにくい汚れが蓄積しています。 また、ホコリと水が混ざることで発生する黒ずみやカビも多く、家庭用の洗剤だけでは落としきれないケースも少なくありません。 業者に依頼するメリット 鏡のウロコや水垢もプロの専用洗剤でピカピカに仕上げられる 排水口の奥まで分解・洗浄され、臭いの元もスッキリ除去 カビや黒ずみを徹底除去し、清潔で衛生的な空間が実現 日常的に使うスペースが美しくなり、毎朝の準備も快適に 洗面所は、家族全員が毎日使うにもかかわらず、掃除が後回しになりがちな場所のひとつです。 定期的にプロの力を借りるで、衛生環境だけでなく日常の快適さもグレードアップします。 「気づかない汚れ」を可視化し、1年に1〜2回のメンテナンスで、きれいな空間を保ちましょう。 ベランダ・バルコニーのクリーニング相場は、約10,000円〜15,000円前後です。 屋外にあるため、風で運ばれてきた土ぼこり・落ち葉・排水溝の詰まりや苔などが溜まりやすく、雨風にさらされる分だけ汚れの蓄積スピードも早いのが特徴です。 ベランダは日常生活であまり掃除をしない人も多く、気づけば床全体が黒ずんでいたり、水はけが悪くなっていたりすることも。 特に集合住宅では排水が詰まって隣室や下階に水漏れするリスクもあり、定期的な清掃が建物トラブルの予防にもつながります。 【ベランダ・バルコニー・玄関まわりの料金相場比較表】 プラン内容 相場目安 主な対応範囲 標準プラン(10㎡未満) 約10,000〜12,000円 床の洗浄・排水口の清掃・手すり・サッシの拭き上げなど 広範囲プラン(10㎡以上または2面以上) 約13,000〜15,000円 上記+大面積対応・植物撤去・網戸や外壁に近い箇所の拭き上げなど 高圧洗浄オプション付き +2,000〜3,000円程度 コケや泥が強い場合に追加されることが多い(床・壁面・排水口など) ※広さ・汚れ具合・水道使用の可否・高所作業の有無などで追加費用が発生するケースもあります。 ベランダは屋外であるがゆえに、見逃されがちなもう一つの生活空間でもあります。 業者に依頼するメリット 長年溜まった黒ずみ・コケ・土ぼこりを一掃して見た目が大幅改善 排水口や溝の詰まりを解消し、水はけ・通気性もスムーズに 高圧洗浄によって雑菌や虫の発生リスクも抑制 清掃後はバルコニーを洗濯干し・ガーデニングなどに快適活用できる とくに排水・通気・防カビの観点からも、半年〜1年に1回の専門クリーニングが推奨されます。 雨風やホコリによる劣化を防ぎつつ、美しく快適な空間を維持するためにも、ぜひ早めの清掃をご検討ください。 水回りセットプランの料金相場|個別よりどれくらいお得? 水回りセットプランの相場は、2点セットで約28,000〜32,000円、4点セットでは約52,000〜60,000円前後が一般的です。 単品で依頼するよりも総額で3,000〜12,000円ほど安くなるケースが多く、ハウスクリーニングを効率よく依頼したい人に人気のプランです。 水回りのクリーニングは、キッチン・浴室・トイレ・洗面所・換気扇など、使用頻度が高く汚れがたまりやすい場所に集中しています。 これらをまとめて依頼できるのが水回りセットプランで、作業が一度に完了するだけでなく、個別に頼むよりも料金が割安になるのが最大の魅力です。 【水回りクリーニングセット料金相場比較表】 プラン構成 セット価格 単品合計目安 割引幅 2点セット(例:キッチン+換気扇) 約28,000〜32,000円 約30,000〜36,000円 約2,000〜4,000円お得 3点セット(例:キッチン・浴室・換気扇) 約40,000〜48,000円 約46,000〜54,000円 約5,000〜8,000円お得 4点セット(例:浴室・キッチン・トイレ・洗面所) 約52,000〜60,000円 約62,000〜70,000円 約8,000〜12,000円お得 ※業者によっては「点数自由選択」「作業時間制プラン」「防カビコーティング付き」などもあり。※季節限定キャンペーン・早期割引などでさらにお得になることもあります。 セットプランは、掃除にかかるコストと労力の両方を抑えながら、快適な住環境を取り戻すための最適な方法です。 セットプランのメリット まとめて依頼することで総額の負担を抑えられる 作業日数が短縮され、立ち会いの回数も最小限に 水回り全体が一気にリフレッシュでき、清潔感が一段アップ 業者によっては定期清掃や防カビ加工とセットでよりお得に 「どの箇所も少しずつ汚れてきたけど、全部は無理かも…」と感じているなら、ぜひ水回りまとめての依頼を検討してみてください。 ハウスクリーニング相場より安くする4つの実践テクニック ハウスクリーニングの費用をできるだけ安く抑えたい方は、以下4つのポイントを確認してみてください。 4つの実践テクニック 複数箇所をまとめて依頼して「セット割」を活用する オフシーズン(閑散期)を狙えば料金が下がる傾向に 掃除しやすい環境に整えておくことで追加料金を防ぐ 必ず複数社から無料見積もりを取り比較するのが鉄則 セット割引は、複数箇所をまとめて依頼することでお得になる代表的な方法です。 セット割引では、公式サイトや予約ホームページで「セット割対象箇所」を事前に確認しておくと安心です。 また、ハウスクリーニングの費用を抑えるテクニックを実践する際は以下のようなことに気を付けましょう。 費用を抑えるテクニックを実践する際の注意点 セット割引を利用するときの注意点 すべての組み合わせが割引対象ではない 不要な箇所まで依頼してしまう恐れ 割引は期間限定・地域限定の可能性あり 閑散期を狙うときの注意点 直前依頼は予約が埋まっていることも 閑散期はスタッフが少なく対応が雑な場合あり 台風等で作業延期の可能性 掃除しやすい環境に整える際の注意点 片づけすぎて掃除範囲を誤解されることも 配線や配管の移動で破損リスク 「これも片づけ対象だった」と後から気づく可能性 複数社に見積もりを取って比較する際の注意点 見積もりを取りすぎて選べなくなる 個人情報の過剰な入力を求められることも 価格だけで選ぶと質が悪い場合も ここからは4つのポイントを詳しく説明していきます。 複数箇所をまとめて依頼して「セット割」を活用する ハウスクリーニングの料金を抑える方法として、もっとも実践的なのが「セット割」を活用することです。 キッチン・換気扇・浴室・トイレなど、複数の水回りをまとめて依頼することで単品ごとに頼むよりも3,000円〜10,000円程度安くなるケースは少なくありません。 この割引は、業者側が一度の訪問で複数作業を効率的にこなせるため、移動コストや人件費を抑えられることに起因しています。 また、同日に複数スタッフで作業することで、全体の作業時間も短縮されるメリットがあります。 業者によっては、「3点セットで1万円割引」や「2点目半額キャンペーン」などの期間限定プランを提供していることも。 公式サイトや予約フォームをチェックして、希望する場所がセット割に対応しているか事前に確認することが大切です。 汚れが気になっている箇所が2〜3カ所以上ある場合は、まとめて依頼するほうが結果的にお得。 金額面だけでなく、時間・手間・仕上がりの一体感という意味でも、セットプランの活用は非常に効率的な選択といえるでしょう。 オフシーズン(閑散期)を狙えば料金が下がる傾向に ハウスクリーニングを少しでも安く依頼したい場合、時期の選び方が大きなカギを握ります。 実は、ハウスクリーニング業界には繁忙期と閑散期があり、依頼が集中するシーズンと比較的落ち着いている時期とで料金や予約状況に明確な差が生まれます。 一般的に、3月〜4月の引越しシーズンや11月〜12月の年末大掃除シーズンは、業者の予約が取りにくくなる一方で料金がやや高めに設定される傾向にあります。 反対に、6月〜7月・1月〜2月といった中間月は比較的予約が取りやすく、割引プランやキャンペーンが展開されやすいタイミングです。 このようなオフシーズンに依頼すれば、通常より数千円〜1万円前後安くなることも珍しくありません。 また、予約も比較的スムーズに取りやすく、希望日時に合わせやすいという利点もあります。 「今すぐではないけれど、いつか掃除しようと思っている」という方は、あえて繁忙期を避けてスケジュールを調整することで、費用面でもサービス面でもお得な依頼が実現できます。 掃除しやすい環境に整えておくことで追加料金を防ぐ ハウスクリーニングを依頼する際、掃除のしやすさ=作業効率の良さがそのまま料金に影響することをご存じでしょうか? 実際、多くの業者では家具の移動や養生が必要な場合に追加料金が発生するケースがあります。 たとえば、キッチン周辺に大型の食器棚やゴミ箱が密集していたり浴室にシャンプーボトルやおもちゃが多数置かれていたりすると、清掃前の準備に時間と労力がかかってしまうため追加費用が上乗せされやすくなります。 また、洗面台やトイレの収納スペースが開けられない、床面が雑貨で覆われている、といった状況も同様です。 こうした事態を防ぐためにも、事前に私物を片づけて掃除しやすい環境を整えておくことが重要です。 重たい家具などの移動までは不要ですが、作業範囲がスムーズにアクセスできるだけで追加費用の回避や作業時間の短縮につながります。 結果として、料金を抑えながらも高品質なクリーニングが受けられるため、「任せっぱなし」ではなく、事前の一手間がコストパフォーマンスに直結するといえるでしょう。 必ず複数社から無料見積もりを取り比較するのが鉄則 ハウスクリーニングの料金を適正に、かつ相場より安く抑えたいなら、「相見積もり(あいみつもり)」は必須のステップです。 同じ間取り・清掃内容でも、業者によって料金やサービス内容には1万円以上の差が出ることもあり、最初から1社だけに決めてしまうのは非常にもったいない判断です。 現在では、「一括見積もりサイト」や「比較サービス」などを利用すれば、無料で3〜5社の見積もりをまとめて確認できるため、手間なく比較が可能です。 その際、料金だけでなく作業内容の詳細・所要時間・オプション料金・保証内容なども一緒にチェックするとよいでしょう。 また、複数社に見積もりを依頼することで、価格交渉がしやすくなる点も見逃せません。 「他社ではこの価格だった」と提示することで、割引や追加サービスの提案を受けられることもあります。 ただし、極端に安すぎる見積もりには注意が必要です。 安価な裏に「清掃範囲が限定されている」「アフター保証がない」などの落とし穴があるケースもあるため、内容のバランスをしっかり見極めることが大切です。 失敗しない!ハウスクリーニング業者を選び方の3つ ハウスクリーニング業者を探す際は失敗しないためにも以下のポイントをおさえて選ぶのがおすすめです。 選び方の3つ 料金と作業範囲が明確に提示されているか確認 損害賠償保険・保証制度の有無を確認 口コミ・評判で利用者のリアルな声を確認する また、以下に、ハウスクリーニング業者を選ぶ際の「3つのポイント」に対する注意点をそれぞれまとめました。 注意点 「安さ」より「価格に見合ったサービス内容」が重要 料金が極端に安い業者は、清掃の質が低かったり、後から追加費用を請求される場合あり 相場と比べて安すぎる場合は警戒 作業内容・対応範囲を事前に確認 見積もりの段階で作業内容・対象作業・オプション費用を確認 悪サービス内容が曖昧なまま契約するとトラブルに 複数のサイトやSNS・比較サイトなどいろんなサイトを確認 やらせレビューやステマの可能性もあり 悪い口コミがまったくない業者も逆に不自然なので注意 参考:国民生活センター│ハウスクリーニングのトラブルにご注意 これらの注意点を意識しておけば、価格・対応・サービス品質のバランスが取れた、納得できる業者選びがしやすくなります。 迷ったときは、無料見積もりを複数社から取り、比較検討することが失敗を防ぐ最大のコツです。 以下で失敗しないハウスクリーニングの選び方を詳しく解説していきます。 料金と作業範囲が明確に提示されているか確認 ハウスクリーニング業者を選ぶうえでまず確認すべきなのは、「料金」と「作業範囲」の明確さです。 Webサイトや見積書で、どの箇所を、どこまで、どんな方法で清掃するのかがはっきりと記載されているかをチェックしましょう。 「浴室クリーニング:9,000円」とだけ書かれていても、鏡のウロコ取りは別料金なのか、換気扇の中まで対応してくれるのかが不明瞭なままでは、あとから思わぬ追加費用が発生する可能性もあります。 信頼できる業者は、事前に標準作業の範囲と追加料金がかかる条件をきちんと説明してくれます。 また、汚れ具合や間取りの特徴などをヒアリングした上で、最適なプランを提案してくれるところは顧客本位といえるでしょう。 とくに注意したいのは、「定額パック」とうたっていても、実際にはオプションが多く最終的に予想以上の金額になってしまう業者です。 見積もり時には、清掃箇所・使用薬剤・作業時間・保証の有無まで、細かく確認しておくと安心です。 曖昧な説明しかない業者よりも、最初から内容が具体的で、相談にも柔軟に応じてくれる業者のほうが、結果的に満足度が高くなりやすいといえるでしょう。 損害賠償保険・保証制度の有無を確認 ハウスクリーニングは専門の道具や洗剤を使った作業が多く、万が一、住宅設備や家具を破損してしまうリスクもゼロではありません。 そのため、依頼先を選ぶ際には損害賠償保険や作業保証制度の有無を必ず確認することが重要です。 実際に起こりうるトラブルとしては、鏡のコーティング剥がれ、床材の変色、水漏れや配線の不具合などが挙げられます。 こうした万が一の事故に対し、補償の対象になるか・どこまでカバーされるか・請求の流れはどうかなど、事前に説明がある業者は信頼できるといえるでしょう。 とくに個人事業主や格安業者の中には、保険未加入のケースも少なくありません。 その場合、トラブルが起きても泣き寝入りになってしまう可能性があるため、注意が必要です。 また、大手業者の中には、作業後の仕上がりに不満がある場合に再訪対応をしてくれる「再清掃保証」を導入しているところもあります。 料金の安さだけでなく、こうした「もしも」のサポート体制も重視することが、後悔しない選び方のポイントといえるでしょう。 口コミ・評判で利用者のリアルな声を確認する ハウスクリーニングの満足度を大きく左右するのが、実際に作業を担当するスタッフの対応力や人柄です。 Google Map口コミやハウスクリーニングのマッチングサイトで利用者のリアルな声を確認することが重要です。 見積もり対応の早さ、問い合わせ時の受け答え、当日の挨拶や説明の丁寧さなど、料金や作業範囲には現れにくい「人」の要素が、サービス品質に直結します。 とくに、施工前後の対応や、トラブル時のフォロー体制について言及されている投稿は、業者の姿勢を知るうえで参考になります。 また、「問い合わせの返信が早かった」「説明がわかりやすかった」といった点も、信頼できる業者を見極める指標になります。 もう1つ注目すべきは、「指名制度」の有無。 一部の業者では、過去に評価の高かったスタッフを再指名できるサービスを導入しており、継続的に安心して依頼できる体制が整っています。 ネット上には価格比較に偏った情報も多いため、実際の利用者の声や細かな対応面まで調べることが、満足度の高い業者選びの近道です。 まとめ ハウスクリーニングの料金相場は、間取り・清掃箇所・住まいの状況によって大きく変動します。 費用を抑えるためには、空室時の依頼・閑散期の利用・セットプランの活用などが有効です。 また、業者を選ぶ際は「料金の内訳が明確か」「追加費用の条件が提示されているか」「保証制度があるか」など、複数の視点で比較することが大切です。 相場を正しく理解し、自宅の状況に合ったサービスを選ぶことで、費用面・仕上がり面の満足度を高めることができます。 まずは気になる業者の無料見積もりから始めて、無理のない範囲で快適な住空間を手に入れてみてはいかがでしょうか。
記事を読む

2025.10.06コラム
東京都のハウスクリーニング業者ランキング9選|相場料金や安くておすすめのサービスを紹介!
「ハウスクリーニングを頼みたいけど、どこがいいか分からない」と悩んでいる方も多いと思います。 東京都のハウスクリーニングを探す際は以下の選び方で選定してみてください。 東京都ハウスクリーニングの選び方 料金体系と作業内容が明確な業者を選ぶ 口コミや評判をチェックして信頼できる業者を選ぶ 損害賠償保険に加入しているか 女性スタッフの指名ができるか ハウスクリーニングの料金は、「作業範囲」「作業時間」「汚れの程度」などで最終料金が決定します。 想定金額より高くならいためにも、見積もりをしっかり確認したうえで信頼できる業者を選ぶようにしましょう。 また、クリーニング中に故障や損傷があったときの補償について、契約前にしっかりと確認する必要があります。 ハウスクリーニングのトラブルに巻き込まれないように事前にチェックするようにしましょう。 本記事では東京都のハウスクリーニング業者ランキング9選を紹介しています。 初めて利用する方にも分かりやすく「安さ」「サービス内容」を解説しているので参考にしてみてください。 この記事でわかること 選び方がわからない ハウスクリーニング業者の選び方 東京都でおすすめのハウスクリーニング業者が知りたい 東京のハウスクリーニング業者おすすめランキング9選 業者のマッチングサイトが知りたい 東京のハウスクリーニング業者おすすめ3選【マッチングサイト編】 株式会社デルフィーノケアについて 株式会社デルフィーノケアでは、独自の抗ウイルス・抗菌剤「デルフィーノ」を用いて、医療・教育・オフィスなど多様な現場の衛生環境を改善する企業です。 お問い合わせはこちら▶ 法医解剖や感染現場で培った技術を活かし、抗菌・防臭・防カビ施工を全国で展開しています。 詳細な事例はこちら▶ 当記事では上記の知見を活かし安心・安全な環境づくりの一環としてハウスクリーニングに関する情報をご紹介しています。 ハウスクリーニングとは? ハウスクリーニングとは、専門業者が住宅内の汚れやカビ・ホコリなどを専用の洗剤や機材を使って徹底的に清掃するサービスのことを指します。 日常的な掃除では落としきれないガンコな汚れや、見えづらい場所のカビ・油汚れなども対象になります。 家事代行サービスと混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。 ハウスクリーニングと家事代行の違い ハウスクリーニング「専門技術による徹底清掃」が主な目的で専門的な機材や技術を使用 家事代行「日常的な掃除・片付け・洗濯」などの家事をサポート 特に引越しや退去前などの「原状回復」においては、物件オーナーや不動産会社からプロのハウスクリーニングを求められることもあります。 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)なども、清掃の重要性を物件管理の一環として明記しています。 一方、ハウスクリーニングは「専門技術による徹底清掃」が主な目的で、高圧洗浄や分解清掃なども行われます。 ハウスクリーニングを活用することで、住まいの衛生環境を整え快適かつ健康的な生活空間を実現することができます。 プロに任せるという選択は、忙しい現代人にとって合理的かつ効率的な暮らし方のひとつといえるでしょう。 東京のハウスクリーニング業者おすすめランキング9選 東京都内に200店舗以上あるハウスクリーニング業者の中から選ぶのはたいへんだと思います。 本記事では以下選定基準で東京のハウスクリーニング業者おすすめランキング9選を選定しました。 選定基準 料金プランが安いか 土日対応しているか 損害賠償保険に加入しているか 女性スタッフの指名ができるか たくさんありすぎて悩んでいる方はぜひ、参考にしてみてください。 業者名 特徴 料金 キャンセル料 土日祝対応 損害補償 女性スタッフ指名 決済方法 エリア おそうじ革命詳しくはこちら 固定料金制を採用しているから追加費用がかからない エアコン:9,980円~キッチン:17,930円~水回り3点セット:38,500円~ 前日まで無料 対応可能 あり 一部対応(要事前相談) 現金、クレジットカード、QRコード決済対応 全国(沖縄・一部離島を除く) おそうじ本舗詳しくはこちら 全国1,800店舗以上を展開する業界最大級のネットワーク エアコン:9,900円~キッチン:19,800円~水まわりのお掃除:19,800円~ 作業2日前まで無料 対応可能 あり 基本不可(※一部相談対応可能) 現金・クレジットカード・一部QR決済 全国(離島・一部地域を除く) 東京ガスのハウスクリーニング詳しくはこちら WEB注文で最短3日後から訪問可能 エアコン:13,200円~キッチン:19,800円~水まわり3点セットA:44,000円~ 前日まで無料 対応可能 あり 不可 現金、クレジットカード 東京、神奈川、埼玉、千葉(一部除外く) カジタク詳しくはこちら 全国一律の定額料金で事前に費用が明確 エアコン:6,600円~キッチン:3,300円~ 作業2日前まで無料 対応可能 あり 不可 クレジットカード(事前決済) 全国対応(一部離島・山間部を除く) ダスキン詳しくはこちら 清掃業界の老舗ブランドによる信頼性の高いサービス エアコン:15,400円~水まわり:22,000円~ 前日まで無料 対応可能 あり 不可 現金、クレジットカード(店舗により異なる) 全国(一部離島・山間部を除く) ベアーズ詳しくはこちら 安心体制6か条で、初めてでも不安なく利用できる エアコン:11,990円~キッチン:18,920円~ 前日17時まで無料 対応可能 あり 可(Web申込時に指定) クレジットカード、口座振替、現金(条件による) 全国対応(東京都23区は即日対応エリアあり) ユアマイスター詳しくはこちら 細かい条件で業者を絞り込める高い検索性 エアコン:11,800円~ 業者により異なる(2~3日前無料が多数) 対応可能 あり 条件指定可能 クレジットカード・後払い決済に対応 全国(東京エリアは登録数が特に多い) クリーンクルー詳しくはこちら 掃除箇所ごとに自由に組み合わせられるセットプランが充実 エアコン:13,200円~キッチン:19,800円~水まわり:19,800円~ 2日前まで無料 対応可能 あり 不可 現金・クレジットカード・デビットカード・銀行振込電子マネー・QRコード決済 関東・関西・九州ほか主要都市 ハートクリーニング詳しくはこちら 防カビ・防臭イオンコーティングが無料 エアコン:10,780円~ 作業実施日の3日前まで 対応可能 あり 不可 現金・銀行振込 関東・関西・九州中心(エリア詳細は公式要確認) おそうじ革命は固定料金制だから追加料金がかかりにくい おそうじ革命の特徴 固定料金制を採用しているから追加費用がかからない 自社スタッフによる高水準な研修制度と技術力 累計15万件以上の清掃実績で培った高い技術力 メニュー 料金(税込) エアコン 9,980円~ キッチン 17,930円~ 水まわりのお掃除 17,930円~ お部屋まわり 7,700円~ 水回り3点セット 38,500円~ おそうじ革命は、全国展開しているハウスクリーニング専門業者で、利用者にとってわかりやすく安心な「固定料金制」を採用している点が大きな特徴です。 作業時間や汚れ具合にかかわらず料金は事前に確定しており、現地での追加請求などが発生しにくい料金体系となっています。 これは、初めてプロのクリーニングを依頼する人にとっても、心理的なハードルを下げる要素のひとつです。 また、おそうじ革命ではすべての作業を自社の専任スタッフが対応しており、スタッフは入社時から実技を含む研修を受けた上で現場に出ています。 これによりサービスの品質を均一に保ちつつ、利用者への丁寧な対応や清掃の技術水準を維持する体制が整っています。 細やかな配慮と高精度な作業品質につながっており、リピーターからの信頼も厚い企業です。 おそうじ革命の公式サイトはこちら おそうじ革命のサービス詳細 駐車料金 原則無料(現地確認あり) キャンセル料 前日まで無料、当日は50%請求 土日祝対応 追加料金なしで対応可能 女性スタッフ指名 一部対応(要事前相談) 損害補償 あり 受付時間 9:00~19:00(年末年始除く) 決済方法 現金、クレジットカード、QRコード決済対応 対応エリア 全国(沖縄・一部離島を除く) プラン料金一覧 ▼エアコンクリーニング サービス 料金 エアコンクリーニング 9,980円~ お掃除機能付きエアコンクリーニング 18,700円~ 防カビ抗菌コート 2,750円~ ▼キッチン回りのお掃除 サービス 料金 キッチンクリーニング 17,930円 レンジフード(換気扇)クリーニング 9,900円~ ▼水回りのお掃除 サービス 料金 お風呂・浴室クリーニング 17,930円~ トイレクリーニング 8,250円 浴室追い焚き配管除菌洗浄 18,700円〜 水垢防止・親水・撥水コーティング 3,850円~ 洗濯機分解クリーニング 17,600円~ 浴室乾燥機クリーニング 11,000円 洗面所クリーニング 8,250円 ▼お部屋回りのお掃除 サービス 料金 ベランダクリーニング 7,700円~ 除菌・消臭クリーニング 3,850円 空室清掃 1㎡:550 円~ シャンデリア・照明器具クリーニング 器具によりお見積りいたします 床・フロアクリーニング 1㎡:330 円~ ガラス・サッシクリーニング 3,850円 壁紙復元塗装 15,400円~ ご利用の流れ STEP お申し込み・お問い合わせ フォームまたは電話から依頼可能。電話番号:0120-963-933 STEP 内容確認・料金・日程調整 内容確認・料金:お聞きしたエアコンのタイプや台数から、作業詳細と料金をMailまたはTELにてご案内致します。日程調整:お電話またはメールでご相談しながら作業日時を決定します。※メールに関しては、電話に比べてタイムラグがあるため、調整が少々遅れる場合がございます。予めご了承ください。 お見積りの料金でご了承いただいた時点でのスケジュール空き状況をお知らせします。お見積り金額は出張費、消費税全て込みになります。 STEP 作業実施・お支払い 作業実施:作業前に再度内容確認を行います。サービス後に仕上がりのチェックをお願いします。お支払い:一般家庭の方【作業終了後現金お取引】/【作業終了後クレジットカード決済】いずれかでお願いします。 作業前※クレジットカード決済を希望のお客様は事前にご連絡ください。企業様は別途ご相談ください。 STEP クリーニング終了 終了後に仕上がりのチェックをしていただきます。 作業の仕上がりに納得いただけない場合は再作業させていただきます。 注意事項 ※お申込前に下記注意事項を必ずご確認ください!以下の様な場合はお承けできません。 ・設置している高さが2.6メートル以上の場合。(通常3段脚立で届く範囲)※お客様の方で3段以上の脚立をご用意いただける場合、もしくは事前にご相談いただいた場合は可能です。・故障しているエアコン。・ウインドウ設置型。・エアコンのブレーカーの場所が解らない。※作業日までに、各エアコンごとのブレーカーを一度落としてご確認ください。※業務用は動力、家庭用は一般的なブレーカーボックスです。※壁掛タイプでコンセントがあるタイプは、確認不要です。・分解した部品の洗い場所が無い。※たたみ1畳分あれば大丈夫です。お風呂場やベランダ、お庭、私道など。・東京ガス製品のエアコン。・天井からぶら下がっている室外機(床置きのみお請けできます) 確認事項 作業日の2日前までのキャンセルは無料です。前日キャンセルは作業料金の50%、当日キャンセルは100%のキャンセル料を申し受けます。ご了承ください。弊社もキャンセル料をいただくことは望んでおりません。日程調整は慎重にお願い致します。 壁掛タイプの際、お掃除ロボット機能付でご予約いただき、当日対象のエアコンが一般タイプの場合、返金はできません。事前に調べてからご注文いただくか、弊社で調べますのでエアコンに貼ってあるシールを御覧ください。型番を教えていただけると幸いです。 お掃除ロボット機能付きタイプは状況により完全分解できない場合がごさいます。 エアコン本体洗浄や部品洗いに必要な水道や高圧洗浄機を作動させる為のコンセントを使わせていただくことを予めご了承ください。 2台目以降の金額は同じタイプのエアコンをご注文いただいた場合に限ります。 タバコの臭いが目立つ場合は、悪臭を完全に除去出来ない場合がございます。 製造後10年以上経つエアコンは、如何なる理由があっても保証対象外になります。理由は10年経つと経年劣化が進んでいることやメーカーの部品在庫がなくなるためです。 クリーニングが原因での故障や動作エラーに関して製造から10年以内であれば弊社にて修理対応いたしますが、故障に伴う店舗やオフィスなどの営業補償や慰謝料のお支払は一切行っておりません。予めご了承ください。 業務用など電源をコンセントではなく、動カブレーカーでON/OFFするタイプは、作業日までに必ず、動力ブレーカーを落として電源が切れるかどうかの確認をお願いします。 サービス当日、大雪や台風の場合、当日朝の天気の状態によりますが、バイクや車での発進が困難な場合は延期させていただく場合がございます。その際は改めて日程の調整をさせていただきます。 おそうじ本舗は全国1,800店舗以上を展開する業界最大級のネットワーク おそうじ革命の特徴 全国1,800店舗以上を展開する業界最大級のネットワーク 専門スタッフによる高品質なサービスと丁寧な接客 エアコンから特殊清掃まで幅広い対応メニュー メニュー 料金(税込) エアコン 9,900円~ キッチン 19,800円~ 水まわりのお掃除 19,800円~ お部屋まわり 5,500円~ 外壁手洗い洗浄 44,000円~ お墓のお掃除 19,800円~ おそうじ本舗は、全国に1,800以上の店舗を展開する国内有数のハウスクリーニング専門ブランドです。 大手ならではの信頼性と実績があり、個人宅だけでなくオフィスや商業施設など法人向けの清掃実績も豊富です。 依頼内容に応じて、専門知識をもったスタッフが訪問し安定したサービス品質を提供しています。 サービスメニューの幅広さも特徴的で、エアコンやキッチンといった家庭の定番箇所に加えて、外壁・お墓のお掃除などの特殊クリーニングにも対応可能です。 多様なニーズに対してワンストップで応えられる点は、多忙な家庭にとって大きなメリットといえるでしょう。 また、エリア担当制を採用しており地域密着型のサービスを実現しています。 担当者が固定されることで継続依頼がしやすく、利用者との信頼関係を構築しやすい点も好評です。 全国対応でありながら「顔が見えるサービス」が実現しているのはおそうじ本舗ならではといえます。 おそうじ本舗の公式サイトはこちら おそうじ本舗のサービス詳細 駐車料金 基本無料(有料駐車場使用時は実費負担) キャンセル料 作業日前3日以内のキャンセルにつきましては料金が発生する場合がございます 土日祝対応 対応可(追加料金なし) 女性スタッフ指名 基本不可(※一部相談対応可能) 損害補償 あり 決済方法 現金・クレジットカード・一部QR決済 対応エリア 全国(離島・一部地域を除く) プラン料金一覧 ▼エアコンクリーニング メニュー 料金((税込) 壁掛けタイプエアコン(お掃除機能なし) 1台:11,000円2以上:9,900円 壁掛けタイプエアコン(お掃除機能付き) 1台:19,800円2以上:18,700円 天井埋め込みタイプエアコン 27,500円 ▼パックサービス(まるごとクリーニング) セットメニュー 料金((税込) 換気扇・キッチンクリーニングセット 36,300円 浴室・浴室乾燥機クリーニングセット 27,500円 浴室・洗面台クリーニングセット 28,050円 浴室・追い焚き配管除菌クリーニングセット 41,800円 浴室クリーニング・ウルブロ取り付けセット 73,700円 お引越し前・後 まるごとクリーニング 26,400円〜 在宅まるごとクリーニング 39,600円〜 ▼水まわりのお掃除 メニュー 料金(税込) お風呂のお掃除 浴室・追い焚き配管除菌セット 41,800円 風呂・浴室クリーニング 19,800円 浴室(風呂釜)の追い焚き配管除菌クリーニング 25,300円 ウルブロ取り付け 62,700円 浴室乾燥機クリーニング 11,000円 トイレのお掃除 トイレ・壁紙染色セット 23,100円 トイレリニューアルコーティング 16,500円 洗面台のお掃除 洗面台クリーニング 9,350円 ▼洗濯機 メニュー 料金((税込) サービス範囲 縦型洗濯機クリーニング 12,100円 洗濯機本体の外側・内側/脱水槽(分解を伴わない洗浄) ドラム式洗濯機クリーニング 18,700円 洗濯機本体の外側・内側/脱水槽(分解を伴わない洗浄) ドラム式乾燥機能分解クリーニング【Panasonic限定】 27,500円 脱水槽・洗濯槽(分解を伴わない洗浄)/洗濯機本体外側・内側(分解→洗浄)/乾燥ダクト(分解→高圧洗浄) ※オプションは公式を確認してください ▼キッチン メニュー 料金((税込) レンジフード・換気扇のお掃除 換気扇・キッチンクリーニングセットプラン 36,300円 レンジフード・換気扇クリーニング 19,800円 キッチンのお掃除 キッチンクリーニング 19,800円 冷蔵庫のお掃除 冷蔵庫クリーニング 11,000円 食器洗い乾燥機のお掃除 食器洗い乾燥機クリーニング 11,000円 ※オプションは公式を確認してください ▼お部屋のお掃除 メニュー 料金(税込) フローリングクリーニング(10帖以下一律料金) 13,200円 ソファ・椅子クリーニング(通常2人掛け) 5,500円 カーペットクリーニング(10帖以下一律料金) 16,500円 壁紙染色(20㎡以下一律料金) 22,000円 壁紙クリーニング(20㎡以下一律料金) 11,000円 ガラス・サッシクリーニング 11,000円 白木クリーニング(6帖以下一律料金) 75,900円 畳除菌クリーニング(6帖以下一律料金) 13,200円 換気ダクトクリーニング(1経路) 12,100円 空気清浄機クリーニング 11,000円 ▼コーティング メニュー 料金(税込) リニューアルコーティング 浴室リニューアルコーティング 71,500円 キッチンリニューアルコーティング 47,850円 トイレリニューアルコーティング 16,500円 洗面台リニューアルコーティング 17,050円 フロアコーティング フロアコーティング(1帖あたり) 8,800円 UVコーティング(1帖あたり) 12,100円 フローリング補修(リペア)※5箇所 11,000円 ▼その他 メニュー 料金(税込) 外壁手洗い洗浄 44,000円 光触媒抗菌コーティング 10帖まで一律 33,000円 ベランダ・外回り高圧洗浄 11,000円 お墓のお掃除 19,800円 ご利用の流れ STEP 無料お見積り 当サイトの各ハウスクリーニングサービスページから、お見積りカートをご利用いただき、ご依頼ください。 お見積りカートよりお見積りをご依頼いただくと、おそうじ本舗よりお客様へ確認メールが届きます(万が一、確認メールが届かない場合は、お申し込みが失敗している可能性がありますので、再度お申し込みください)。 STEP ご訪問日のご連絡 担当スタッフより、お客様にお電話させていただきます。ご依頼の場所へお伺いする日程など、詳細をお伺いいたします。 携帯電話よりご連絡を差し上げる場合がございますので、予めご了承ください。 おそうじ本舗では最終お見積り確認とクリーニングを同日に行っております。 STEP クリーニング 当サイトの各ハウスクリーニングサービスページから、お見積りカートをご利用いただき、ご依頼ください。 クリーニングを始める前に、クリーニング時間・料金・サービス内容の確認をします。 相違がなければ、クリーニングを開始します。 クリーニング終了後、お客様に仕上がりを確認していただきます(万が一、やり残しなどがあった場合は再度クリーニングをします)。 STEP お支払い 現金またはクレジットカード・電子決済でお支払い頂きます ご利用可能なクレジットカード・電子決済は、各店舗により異なります。お支払い方法の利用可否や種類については、各店舗にご確認ください。 東京ガスのハウスクリーニングはWEB注文で最短3日後から訪問可能 おそうじ革命の特徴 WEB注文で最短3日後から訪問可能 セットメニューが充実しており目的に合わせて選びやすい 東京ガスグループ運営の信頼感とサービス品質 メニュー 料金(税込) エアコン 13,200円~ キッチン 19,800円~ 水まわり3点セットA 44,000円~ 東京ガスのハウスクリーニングは、住宅インフラに精通した東京ガスグループが手がける生活サポートサービスです。 清掃対象は水回りからレンジフード、エアコンまで幅広く対応しており家庭のあらゆる清掃ニーズに応えます。 このサービスは、WEB注文で最短3日後から訪問可能で急な引っ越しや予定変更にも柔軟に対応できます。 セットプランが豊富に用意されているのも大きな特長です。 キッチンや浴室を個別に頼むこともできますが、水まわり4カ所パックなどのまとめて依頼できるプランが人気を集めています。 運営元が東京ガスグループであることから、住宅設備に関する知見が豊富で清掃においても安全性と技術力の両面で高い評価を得ています。 予約や支払いの手続きも簡潔で、WEB上で見積もりから申し込みまで完結できます。 東京ガスのハウスクリーニングの公式サイトはこちら 東京ガスのハウスクリーニングのサービス詳細 駐車料金 原則無料、実費請求の可能性あり キャンセル料 2日前の17時まで無料、2日前の17時以降は有料 土日祝対応 追加料金なしで対応 女性スタッフ指名 不可 損害補償 あり 決済方法 現金、クレジットカード 対応エリア 東京、神奈川、埼玉、千葉(一部除外) 料金プラン一覧 ▼エアコン メニュー / 作業時間(めやす) 料金(税込) 壁掛けエアコン(お掃除機能なし)約1時間20分 13,200円 壁掛けエアコン(お掃除機能付き)約2時間 22,000円 天井埋め込みエアコン(お掃除機能なし・1方向)約2時間 27,500円 天井埋め込みエアコン(お掃除機能なし・2方向)約2時間15分 30,800円 天井埋め込みエアコン(お掃除機能なし・4方向)約2時間30分 38,500円 天井埋め込みエアコン(お掃除機能付き・1方向)約3時間 36,300円 天井埋め込みエアコン(お掃除機能付き・2方向)約3時間15分 39,600円 天井埋め込みエアコン(お掃除機能付き・4方向)約3時間30分 47,300円 ▼キッチン・レンジフード メニュー / 作業時間(めやす) 料金(税込) レンジフード(お掃除機能なし)約1時間30分 17,600円 キッチン(I型・L型・U型)約2時間20分 19,800円 ▼浴室 メニュー / 作業時間(めやす) 料金(税込) 浴室(鏡のウロコ取りなし)約2時間20分 17,600円 浴室(鏡のウロコ取りあり)約2時間35分 22,000円 ▼洗濯機 メニュー / 作業時間(めやす) 料金(税込) 洗濯機(ドラム式または縦型(乾燥機能なし))約1時間30分 13,200円 洗濯機(縦型(乾燥機能付き))約2時間 17,600円 ▼その他(屋内) メニュー / 作業時間(めやす) 料金(税込) トイレ※1約45分 9,900円 洗面所※1約45分 9,900円 ソファー(本体・布地)約1時間30分 13,200円 【無料】空き家管理 現地カウンセリング約1時間30分 0円 ※1:単体ではご注文いただけません。他メニューと合わせてご注文ください。 ▼その他(屋外) メニュー / 作業時間(めやす) 料金(税込) 窓・網戸・サッシ(2セット)約1時間50分 13,200円 ベランダ約1時間30分 13,200円 駐車場約1時間30分 13,200円 エントランス約1時間30分 13,200円 排水管洗浄(戸建住宅専用・敷地内駐車スペースあり)約2時間15分 55,000円 排水管洗浄(戸建住宅専用・敷地内駐車スペースなし)約2時間15分 60,500円 網戸の張替え(1枚)約45分 13,200円 ▼セットメニュー メニュー / 作業時間(めやす) 料金(税込) エアコン&レンジフードセットA約2時間40分 29,260円 エアコン&レンジフードセットB約3時間10分 37,620円 浴室&レンジフードセットA約3時間30分 33,440円 浴室&レンジフードセットB約3時間45分 37,620円 浴室&洗濯機セットA約3時間30分 29,260円 浴室&洗濯機セットB約3時間45分 33,440円 浴室&洗濯機セットC約3時間30分 33,440円 浴室&洗濯機セットD約3時間45分 37,620円 水まわり3点セットA約4時間35分 44,000円 水まわり3点セットB約4時間50分 47,520円 水まわり4点セットA約4時間35分 48,675円 水まわり4点セットB約4時間50分 51,975円 水まわり5点セットA約4時間35分 56,100円 水まわり5点セットB約4時間50分 59,400円 水まわり3点セットA&エアコン(お掃除機能なし)約4時間25分 51,150円 水まわり3点セットA&エアコン(お掃除機能付き)約4時間25分 57,750円 水まわり3点セットB&エアコン(お掃除機能なし)約4時間40分 54,450円 水まわり3点セットB&エアコン(お掃除機能付き)約4時間40分 61,050円 水まわり4点セットA&エアコン(お掃除機能なし)約5時間5分 58,575円 水まわり4点セットA&エアコン(お掃除機能付き)約5時間5分 65,175円 水まわり4点セットB&エアコン(お掃除機能なし)約5時間20分 61,875円 水まわり4点セットB&エアコン(お掃除機能付き)約5時間20分 68,475円 水まわり5点セットA&エアコン(お掃除機能なし)約5時間5分 61,600円 水まわり5点セットA&エアコン(お掃除機能付き)約5時間5分 67,760円 水まわり5点セットB&エアコン(お掃除機能なし)約5時間20分 64,680円 水まわり5点セットB&エアコン(お掃除機能付き)約5時間20分 70,840円 当日の流れ STEP 到着前 到着の約10分前に、お客さまにショートメッセージが届きます。 ※携帯電話番号をお伺いしたお客さまに限ります。 STEP 入室 サービススタッフが到着したら、まず従事者証を提示しますので、ご確認ください。 STEP クリーニング内容確認 クリーニング内容の確認をします。お客さまの気になる箇所をお聞かせください。 STEP クリーニング クリーニングを実施します。 お客さまは普段通りお過ごしください。 気になることがあれば、いつでもお声がけください。 STEP 仕上り確認 クリーニングが終わりましたら、仕上り具合をご確認ください。 汚れ残りなどがありましたら、その場でやり直します。 STEP クリーニング終了・退室 お客さまのサインをいただいてクリーニング終了です。 STEP アンケート回答 サービス品質の向上のため、お客さまアンケートにご協力をお願いします。 カジタクは全国一律の定額料金で事前に費用が明確 カジタクの特徴 全国一律の定額料金で事前に費用が明確 満足できなければ無料で再清掃してくれる「仕上がり満足保証」 イオングループが運営する安心のサービス体制 カジタクは、イオングループが運営する生活支援サービスのひとつでハウスクリーニングを全国で展開しています。 料金体系は全国一律の定額制で、掃除箇所や地域によって価格が変動しないため誰でも安心して申し込むことができます。 最大の特長は仕上がりに納得できなかった場合に再清掃を無料で行ってくれる「仕上がり満足保証」が用意されている点です。 作業内容や品質に対して高い基準を設けているため、利用者はリスクを感じることなく依頼できます。 提供メニューはエアコン、浴室、レンジフードなどの基本的なクリーニングをはじめ水回りセットや引っ越し前後の空室クリーニングなど多彩に用意されています。 すべてのメニューが事前見積もり不要でオンラインで予約から決済まで完結するのも忙しい人にとっては大きな利点です。 東京を含む全国の主要都市で対応しており、サービス対象エリアは年々拡大しています。 決済方法は事前のクレジットカード払いが基本となっており、店舗でも購入可能なためギフトとしての利用も増えています。 カジタクの公式サイトはこちら カジタクのサービス詳細 駐車料金 基本無料(ただし駐車スペース必須) キャンセル料 作業2日前まで無料、以降は50〜100% 土日祝対応 対応可能(追加料金なし) 女性スタッフ指名 不可 損害補償 最大1億円まで補償 決済方法 クレジットカード(事前決済) 対応エリア 全国対応(一部離島・山間部を除く) 料金プラン一覧 ▼エアコン メニュー 料金 実施時間(目安) 室外機 6,600円 20〜30分 防虫キャップ取り付け 1,650円 5〜10分 オールチタンコーティング 3,300円 10〜15分 ▼キッチン メニュー 料金 実施時間(目安) 魚焼きグリル 3,300円 20〜30分 電子レンジ 3,300円 10〜15分 キッチンの小窓(~2m2) 3,300円 10〜20分 ▼トイレ・洗面所 メニュー 料金 実施時間(目安) トイレまたは洗面所の換気扇 3,300円 10〜20分 ▼浴室 メニュー 料金 実施時間(目安) 浴槽エプロン内部 6,600円 20〜30分 浴室乾燥機付き換気扇 9,900円 60分 浴室の換気扇 3,300円 10〜20分 浴室の防カビ 3,300円 5〜10分 浴室備品 3,300円 10〜20分 浴室の小窓(~2m2) 3,300円 10〜20分 ▼全サービス対応 メニュー 料金 実施時間(目安) トイレ 9,900円 45分 洗面所 9,900円 45分 窓・サッシ・網戸セット 1ヶ所 9,900円 30分 予約の流れ STEP ネットでご注文 プロにおまかせしたい箇所をご注文!エアコンとレンジフードなど、複数箇所の予約も可能。もちろん、PC・スマホどちらも対応!Amazon Payにも対応しているので、おなじみのアカウントで購入も安心、スムーズに行うことができます。 STEP ネットで日時予約 見積り訪問なし!お掃除に来て欲しい日時を選択、必要情報を入力して予約完了。2回目からは最短2分で予約可能。※ サービス購入後、予約が可能となります。※ 希望日時がない場合はキャンセルも可能です。 STEP 清掃のプロがサービス実施 予約日時にハウスクリーニングのプロがサービス実施。サービス前後に、お客さまと一緒に内容、範囲、正常動作等の確認を行います。※お伺いするにあたりスタッフよりご連絡をさせていただく場合がございます。 ダスキンは清掃業界の老舗ブランドによる信頼性の高いサービス ダスキンの特徴 清掃業界の老舗ブランドによる信頼性の高いサービス 国家資格保有者や専門スタッフによる高品質な作業 個人宅から法人まで幅広い実績と対応力 ダスキンは、清掃業界において長い歴史と実績を持つ全国規模の企業です。 その中でもハウスクリーニング部門は「サービスマスター」の名称で展開されており、専門的な教育を受けたスタッフが家庭内のあらゆる清掃に対応しています。 特にエアコン・浴室・キッチンといった水回りの清掃に強く、長年の経験と知見に裏打ちされた確かな技術が評価されています。 社内研修に加えビルクリーニング技能士といった国家資格を持つスタッフも在籍しており、作業ごとに明確な基準が設けられている点も安心材料のひとつです。 また、個人宅だけでなく医療機関やオフィス、商業施設などの法人対応にも実績があり高水準なサービス品質を個人向けにも提供できる体制が整っています。 訪問スタッフの服装やマナーにも配慮があり、家庭内での作業でも不快感を与えない対応が徹底されています。 見積もりは無料で、希望の作業内容や汚れの状態に応じて柔軟に対応されます。 セットメニューのほか、単品メニューの組み合わせも可能なためニーズに合わせたオーダーメイド型の依頼がしやすい点も特長です。 ダスキンの公式サイトはこちら ダスキンのサービス詳細 駐車料金 原則無料、立地により実費請求あり キャンセル料 前日の場合:15%当日の場合:30% 土日祝対応 対応可能、追加料金は原則なし 女性スタッフ指名 不可 損害補償 あり 決済方法 現金、クレジットカード(店舗により異なる) 対応エリア 全国(一部離島・山間部を除く) 料金プラン一覧 ▼エアコンクリーニング|エアコンクリーニング<壁掛けタイプ> 標準料金表 ≪家庭用壁掛け≫自動お掃除機能なし 1台目 15,400円(税込) 2台セット 25,300円(税込) 3台目から追加1台ごとに 12,650円(税込) 3台セット 47,300円(税込) 標準料金表 ≪家庭用壁掛け≫自動お掃除機能付き 1台 26,400円(税込) 2台セット 47,300円(税込) 3台目から追加1台ごとに 23,650円(税込) 3台目 70,950円(税込) 注釈 ※サービス実施日は時期によってご希望に添えない場合がございます。※ 年式やメーカーに関わらず承ります。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 正常動作しないものはお断りする場合があります。※ 動作状況・設置場所などの確認のため、事前に訪問させていただきます。場合によりサービスできないことがありますので、ご了承ください。※ 料金は、ご家庭にある家庭用エアコンを表示しています。※ 作業内容は写真と異なる場合があります。※ ご紹介の作業写真はすべてサービスを分かりやすくご説明するものです。実際の作業におきましては、洗浄液が飛び散らないように養生を行い作業をすすめます。※ その他の機種・室外機につきましては、別途お見積りさせていただきます。※ 汚れによっては完全にとれない場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。地域によりお伺いできないところがございます。土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。あらかじめご了承のほど、何卒宜しくお願いいたします。 ▼エアコンクリーニング|エアコンクリーニング<天井埋込タイプ> 標準料金表 ≪家庭用天井埋込タイプ≫ 1台目 40,700円(税込) 2台セットで 77,000円(税込) 3台目から追加1台ごとに 33,000円(税込) 注釈 ※サービス実施日は時期によってご希望に添えない場合がございます。※ 油煙など特殊な汚れがある場合は、別途料金5,500円(税抜5,000円)を頂戴いたします。※ 作業環境(高所作業・周辺養生等)により別途料金がかかる場合があります。※ 5馬力、14kw、12,500kcalを超える大型のエアコンの場合、上記標準料金の1.2倍の料金で承ります。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 正常動作しないものはお断りする場合があります。※ 動作状況・設置場所・汚れ度合いの確認のため、事前に訪問させていただきます。場合によりサービスできないことがありますので、ご了承ください。※ 作業内容は写真と異なる場合があります。※ その他の機種につきましては、別途お見積りさせていただきます。※ 汚れによっては完全にとれない場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。 ▼水まわり 浴室クリーニング 浴室1室(床面積3m²、高さ2.4m未満) 22,000円(税込)~ オプション ※クリーニング料金にプラス カビ防止コート 5,060円(税込)~ 浴槽追いだき配管内除菌クリーニング 6,600円(税込) 浴槽エプロン内部クリーニング 5,060円(税込) 注釈 ※ サービス実施日は時期によってご希望に添えない場合がございます。※ 汚れによっては完全にとれない場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 料金は標準的な金額を記載しております。機種・素材・ご要望によって料金は変動する場合がありますので、ご了承ください。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。※ 「浴室暖房乾燥機(換気扇)内部クリーニング」は、サービスマスターにて承ります。地域によりお伺いできないところがございます。土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。あらかじめご了承のほど、何卒宜しくお願いいたします。 レンジフードクリーニング(換気扇クリーニング) レンジフードまたはフード付き換気扇1台 (幅95cm未満) 22,000円(税込)~ 注釈 ※ サービス実施日は時期によってご希望に添えない場合がございます。※ 汚れによっては完全にとれない場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 料金は標準的な金額を記載しております。機種・素材・ご要望によって料金は変動する場合がありますので、ご了承ください。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。地域によりお伺いできないところがございます。土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。あらかじめご了承のほど、何卒宜しくお願いいたします。 キッチンクリーニング キッチン1ヵ所(間口3m未満) 20,680円(税込)~ オプション ※クリーニング料金にプラス 食器棚・冷蔵庫表面クリーニング 2,530円(税込)~ キッチン排水管クリーニング 1,980円(税込) 魚焼きグリルクリーニング(皿・網のみ) 2,530円(税込) 注釈 ※ オプションはキッチンクリーニングとセットでお申込みできます。※ オプション販売は、一部適合しないキッチンがあります。※ オプションクリーニング・オプション販売はサービススタッフにお申しつけ下さい。※ サービス実施日は時期によってご希望に添えない場合がございます。※ 汚れによっては完全にとれない場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。※ 料金は標準的な金額を記載しております。機種・素材・ご要望によって料金は変動する場合がありますので、ご了承ください。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 料金は標準的な金額を記載しております。機種・素材・ご要望によって料金は変動する場合がありますので、ご了承ください。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。地域によりお伺いできないところがございます。土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。あらかじめご了承のほど、何卒宜しくお願いいたします。 トイレクリーニング トイレ1室(床面積2m²未満) 1,0340円(税込)~ オプション ※クリーニング料金にプラス 汚れ防止コート(便器内部1台) 3,850円(税込) トイレロータンク内除菌クリーニング 4,400円(税込) 注釈 ※ サービス実施日は時期によってご希望に添えない場合がございます。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 料金は標準的な金額を記載しております。機種・素材・ご要望によって料金は変動する場合がありますので、ご了承ください。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。※ サービスは1回あたり11,000円(税抜10,000円)以上で承ります。(ただし、定期サービスを除きます。)この料金は、加盟店によって異なる場合があります。※ 便器・タンクの大きさや形状、止水栓・給水管・コンセントの位置によっては取り付けできない場合があります。※ 部材を取り付ける際、別途料金が必要となる場合があります。地域によりお伺いできないところがございます。土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。あらかじめご了承のほど、何卒宜しくお願いいたします。 洗面所クリーニング 洗面所1ヵ所(床面積3.5m²未満) 10,340円(税込)~ オプション ※クリーニング料金にプラス 汚れ防止コート(洗面ボウル1台) 2,530円(税込) 注釈 ※サービス実施日は時期によってご希望に添えない場合がございます。※汚れによっては完全にとれない場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。※料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※料金は標準的な金額を記載しております。機種・素材・ご要望によって料金は変動する場合がありますので、ご了承ください。※サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。※サービスは1回あたり11,000円(税抜10,000円)以上で承ります。(ただし、定期サービスを除きます。)この料金は、加盟店によって異なる場合があります。地域によりお伺いできないところがございます。土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。あらかじめご了承のほど、何卒宜しくお願いいたします。 ▼家中いろいろ(セットプラン) ハウスワイドサービス(空き室お掃除) Aセット Bセット ■水まわり(キッチン・レンジフード・バス・トイレ・洗面所)■ガラス・サッシ・網戸 ■水まわり(キッチン・レンジフード・バス・トイレ・洗面所)■ガラス・サッシ・網戸■各部屋掃除機がけ■天井・壁・照明のダスティング■畳・スイッチプレート・ドア拭き上げ ※Aセット・Bセットはモデルプランとなります。お掃除箇所についてはお気軽にお申し付けください。 マンション(Aセット) 1R/1K/1DK 30m² 52,800円(税込)~ 1LDK/2DK 40m² 78,100円(税込)~ マンション(Bセット) 1R/1K/1DK 30m² 59,400円(税込)~ 1LDK/2DK 40m² 85,800円(税込)~ 戸建て(Aセット) 2LDK/3DK 70m² 114,400円(税込)~ 3LDK/4DK 90m² 130,900円(税込)~ 戸建て(Bセット) 2LDK/3DK 70m² 123,200円(税込)~ 3LDK/4DK 90m² 141,900円(税込)~ 注釈 ※ 上記の作業条件を超える場合は、別途お見積りを実施させていただきます。※ 汚れによっては完全にとれない場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 料金は地域・お部屋の広さや間取りによって異なります。※ 料金は標準的な金額を記載しております。機種・素材・ご要望によって料金は変動する場合がありますので、ご了承ください。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。・ハウスワイドサービス作業条件・デザイナーズマンション、メゾネットタイプなど、床面積が大幅に広い場合(1Rで25m²を超えるなど)は別途お見積りさせていただきます。・料金表のサービス料金は全て税込参考料金です。事前にお見積りとサービス内容の確認をさせていただきます。 ▼お部屋・リビング・和室 ガラス・サッシ・網戸クリーニング(表裏の両面を作業) ガラス・サッシクリーニング ガラス1枚 0.5m²未満 1,496円(税込)~ ガラス1枚 1m²未満 2,244円(税込)~ ガラス1枚 2m²未満 2,992円(税込)~ ガラス1枚 3m²未満 3,740円(税込)~ 網戸クリーニング ガラス1枚 0.5m²未満 748円(税込)~ ガラス1枚 1m²未満 1,122円(税込)~ ガラス1枚 2m²未満 1,496円(税込)~ ガラス1枚 3m²未満 1,870円(税込)~ 雨戸クリーニング ガラス1枚 0.5m²未満 1,650円(税込)~ ガラス1枚 1m²未満 1,650円(税込)~ ガラス1枚 2m²未満 1,980円(税込)~ ガラス1枚 3m²未満 2,420円(税込)~ 注釈 ※ 1枚あたりの面積が上記を超える場合は、別途お見積りを実施させていただきます。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 料金は標準的な金額を記載しております。広さや汚れの度合によって料金は上下しますので、ご了承ください。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。※ サービスは1回あたり11,000円(税抜10,000円)以上で承ります。この料金は、加盟店によって異なる場合があります。地域によりお伺いできないところがございます。土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。あらかじめご了承のほど、何卒宜しくお願いいたします。 標準料金表≪フローリング・クッションフロア≫ 6帖 10,081円(税込)~ 10帖 16,703円(税込)~ 注釈 ※ 汚れによっては完全にとれない場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 料金は標準的な金額を記載しております。広さや汚れの度合によって料金は上下しますので、ご了承ください。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。※ サービスは1回あたり11,000円(税抜10,000円)以上で承ります。この料金は、加盟店によって異なる場合があります。地域によりお伺いできないところがございます。土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。あらかじめご了承のほど、何卒宜しくお願いいたします。 カーペットクリーニング ウール・化繊 6帖 10,518円(税込)~ ウール・化繊 10帖 17,474円(税込)~ だんつう 1帖あたり 3,267円(税込)~ 注釈 ※ 汚れによっては完全にとれない場合がありますのでご了承くださいますようお願いいたします。※ 料金は消費税(10%)込みの総額表示となっています。※ 料金は標準的な金額を記載しております。広さや汚れの度合によって料金は上下しますので、ご了承ください。※ サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。※ サービスは1回あたり11,000円(税抜10,000円)以上で承ります。(ただし、定期サービスを除きます。)お申し込みサービスの料金合計が、この料金を下回る場合も11,000円(税抜10,000円)を頂戴しますので、ご了承ください。この料金は、加盟店によって異なる場合があります。地域によりお伺いできないところがございます。土・日・祝日のサービスに関しましては、お受けできないことがございます。あらかじめご了承のほど、何卒宜しくお願いいたします。 お見積りからサービス実施までの流れ STEP 無料お見積りのご依頼 お電話、E-Mailまたは、お問い合わせフォームよりお気軽にお見積りをご依頼いただけます。 STEP お電話にて、ご要望のお聞き取りとお見積りご訪問日の決定 お見積もりをご依頼をいただきますと、担当者から24時間以内(*1)にお電話をいたします。(*2) *1: 日曜・土曜・祝日は除きます。ご了承ください。*2: お電話を差し上げる日は、ご指定いただけます。 お電話にて、お客様のご要望を伺います。また、お見積りのために訪問させていただく日を決めさせていただきます。お客様のご都合の良い日をお聞かせください。 STEP お見積りのご提出 お客様のお宅/事業所へ、専任のマネージャーが訪問し、お客様のご要望・ご希望・ご予算などをお伺いします。サービスについてご説明し、お掃除のご提案とお見積りをいたします。お見積りの内容・料金をご確認のうえ、ご判断ください。サービスの実施について、不安なことやご質問も遠慮なくご相談ください。 STEP 正式なサービスのご依頼・実施 お見積りの内容にご納得いただけたら、サービスをご依頼ください。正式な契約書を交わし、お約束させていただいた日程でサービスを実施いたします。プロのお掃除をご体感ください。 STEP お支払いとキャンセルについて お支払方法お支払いはサービス終了後にお願いしております。サービス内容の変更とキャンセルお見積り依頼では、契約は成立しておりません。お見積り依頼後、担当マネージャーより確認のお電話をさしあげます。変更・キャンセルのある場合は、その際にお申し付けください。 ベアーズは安心体制6か条で初めてでも不安なく利用できる ベアーズの特徴 安心体制6か条で、初めてでも不安なく利用できる 満足度96.2%の実績が証明する高品質な仕上がり 教育制度と接遇研修により、スタッフの品質が安定 ベアーズは、東京都内をはじめ全国で家事代行とハウスクリーニングサービスを展開する大手企業です。 とくに「安心体制6か条」に基づいた仕組みは、サービスに対する不安を最小限に抑えるための制度として注目されています。 安心体制6か条 徹底したプライバシー管理 提示価格保証 お申し込み後も変更・キャンセル可能 手直し保証 サービス後30分以内のフォローコール 誠実なトラブル対応 さらに、利用者満足度は96.2%を記録しており、仕上がりの丁寧さと接客対応の良さが高く評価されています。 これは単なる清掃品質にとどまらず、ベアーズが力を入れるスタッフ教育制度の成果でもあります。 新人研修だけでなく、定期的な接遇トレーニングや技術指導によりサービス水準を全社的に保っているのが特長です。 女性スタッフの指名ができるほか、柔軟な時間対応や土日祝の訪問にも応じており共働き世帯や一人暮らしの方にも使いやすいサービスです。 料金は定額制が基本となっており、希望のメニューを選ぶだけで簡単に予約ができる点も支持されています。 ベアーズの公式サイトはこちら ベアーズのサービス詳細 駐車料金 原則無料、近隣に駐車場がない場合は実費請求 キャンセル料 前日17時まで無料、それ以降は50%〜100% 土日祝対応 追加料金なしで対応可能 女性スタッフ指名 可(Web申込時に指定) 損害補償 決済方法 クレジットカード、口座振替、現金(条件による) 対応エリア 全国対応(東京都23区は即日対応エリアあり) 料金プラン一覧 ▼定期プラン料金 定期プラン料金 プラン名 サービス料金 交通費 合計金額 リセットプロプラン 8,000円 + 消費税 月1回、3時間 27,927円(税込) 注釈 定期プランを1回3時間未満(2時間以上)でのご利用の場合は、1時間あたり9,000円(税抜き)にて承ります。その際の延長料金は30分毎4,500円(税抜き)となります。 サービスの日程変更・キャンセルをご希望の場合は、サービス実施日の前日12時までにご連絡をお願いしております。12時以降に承った場合は、サービス料金100%のキャンセル料が発生いたします。予めご注意ください。 お勤め先が、福利厚生代行サービスをご利用の場合、もしくはベアーズの法人会員企業に該当されるお客様はご優待価格が適用されます。 ▼スポットプラン料金 プラン名 合計金額 エアコンクリーニング 11,990円(税込)~ 家庭用壁掛けエアコン+室外機分解洗浄+防カビコーティング 19,800円(税込)~ キッチン・台所クリーニング 18,920円(税込)~ 換気扇クリーニング 17,600円(税込)~ 浴室(バスルーム)のクリーニング 19,910円(税込)~ トイレクリーニング 10,340円(税込)~ 洗面所クリーニング 10,340円(税込)~ フローリング・ワックスクリーニング 16,500円(税込)~ 絨毯・カーペットクリーニング 25,300円(税込)~ 窓・網戸・サッシクリーニング 7,370円(税込)~ ベランダクリーニング 13,200円(税込)~ おかたづけメガMAX 44,000円(税込)~ お墓清掃・お墓参り代行サービス 30,800円(税込)~ 注釈 サービス料金の消費税は別途申し受けます。 7,000円未満のアイテムのみをご希望の場合は、別途5,000円(税抜き)を申し受けます。 駐車場(駐車スペース)について:サービス当日は作業車にてお伺いいたします。違法駐車による交通渋滞、交通事故、緊急車両の通行妨害を防止する為、お客様に駐車場(駐車スペース)の確保をお願いしております。敷地内に駐車場が無い場合は、有料駐車場(コインパーキング)を利用いたします。その場合、駐車料金の一部(1,018円~2,037円)をお客様にご負担いただいておりますので、予めご了承ください。 サービスの日程変更・キャンセルをご希望の場合は、サービス実施日の前日12時までにご連絡をお願いしております。12時以降に承った場合は、サービス料金100%のキャンセル料が発生いたします。予めご注意ください。 不用品回収サービスも承ります。ご希望の方はお問い合わせ時にご相談ください。(事前予約制) お勤め先が、福利厚生代行サービスをご利用の場合、もしくはベアーズの法人会員企業に該当されるお客様はご優待価格が適用されます。 ▼まとめてお得なパック料金 プラン名 合計金額 キッチン+換気扇パック 34,100円(税込)~ 浴室周り2点パック 28,820円(税込)~ 浴室周り3点パック 38,830円(税込)~ 水周りまるごとパック 69,740円(税込)~ コンロ + 換気扇パック 24,860円(税込)~ ▼全体清掃料金 プラン名 合計金額 引っ越し前後の清掃・空室の全体クリーニング 30,800円(税込)~ 全体清掃・お家全体のクリーニング 46,200円(税込)~ 注釈 サービス料金の消費税は別途申し受けます。 7,000円未満(税抜き)のアイテムのみをご希望の場合は、別途5,000円(税抜き)を申し受けます。 駐車場(駐車スペース)について:サービス当日は作業車にてお伺いいたします。違法駐車による交通渋滞、交通事故、緊急車両の通行妨害を防止する為、お客様に駐車場(駐車スペース)の確保をお願いしております。敷地内に駐車場が無い場合は、有料駐車場(コインパーキング)を利用いたします。その場合、駐車料金の一部(1,018円~2,037円)をお客様にご負担いただいておりますので、予めご了承ください。 サービスの日程変更・キャンセルをご希望の場合は、サービス実施日の前日12時までにご連絡をお願いしております。12時以降に承った場合は、サービス料金100%のキャンセル料が発生いたします。予めご注意ください。 不用品回収サービスも承ります。ご希望の方はお問い合わせ時にご相談ください。(事前予約制) お勤め先が、福利厚生代行サービスをご利用の場合、もしくはベアーズの法人会員企業に該当されるお客様はご優待価格が適用されます。 ご利用の流れ STEP 予約申し込み ホームページのフォームよりお申し込みください。ご要望、お打ち合わせ・サービスの希望日時もお聞かせください。細かなお問い合わせは、お電話も便利です。様々なメニューからご自身に合ったプランをお選びください。 STEP 無料カウンセリング(定期サービス) コーディネーターがお客様のご自宅に訪問。お部屋の状態、作業内容、お客様の予算、ご都合等を考慮し、最適なプランをご提案します。 STEP 人選 お客様のご要望に適したスタッフを人選します。業界TOPクラスのスタッフ体制を誇るベアーズが、長年の実績により構築されたノウハウで、お客様にあったスタッフをマッチングします。 STEP サービス お約束日時にスタッフが訪問し、サービスを行います。定期サービスの場合、初回サービス時に、担当マネージャーが同行し、スタッフへの伝達・サービスの再確認を行います。気になる点等がございましたら、お気軽にお伝えください。 STEP お支払い・アフターケア サービス終了後に、事前登録のクレジットカード、もしくは後払い決済〔コンビニ・郵便局・銀行・LINE Pay〕でのお支払いとなります。ご感想やお気づきの点は、お気軽にお聞かせください。 ユアマイスターは細かい条件で業者を絞り込める高い検索性 ユアマイスターの特徴 細かい条件で業者を絞り込める高い検索性 専門性の高い職人や地域密着型業者が多数登録 見積もりから支払いまで一貫してオンライン完結 ユアマイスターは、ハウスクリーニングをはじめとした「暮らしのメンテナンス」を依頼できるマッチング型プラットフォームです。 東京都内には数百件を超える登録業者があり、価格や対応箇所だけでなく「女性スタッフ対応可」「エコ洗剤使用」などの細かい条件で検索できる点が大きな魅力です。 登録されているのは清掃業専門の職人や地域に根ざした業者が中心でそれぞれのプロフィールや口コミ、実際の施工写真などが掲載されています。 清掃内容に特化したレビューも多く、利用者は具体的な仕上がりをイメージしながら業者を選べます。 サービスの流れはすべてオンラインで完結でき、見積もり相談・日程調整・決済までもがサイト上でスムーズに行えます。 また、事前に提示された料金から追加費用が発生しにくく、トラブル時にはプラットフォームによる補償対応がある点も安心材料のひとつです。 自宅に合った業者を比較検討しながら選べるユアマイスターは、サービス品質と選びやすさの両方を重視したい方におすすめです。 ユアマイスターの公式サイトはこちら ユアマイスターのサービス詳細 駐車料金 原則利用者負担、業者により実費請求あり キャンセル料 業者により異なる(2~3日前無料が多数) 土日祝対応 ほとんどの業者が対応(料金変動少ない) 女性スタッフ指名 条件指定可能(検索時に絞り込み可) 損害補償 ユアマイスター独自の保証制度あり 決済方法 クレジットカード・後払い決済に対応 対応エリア 全国(東京エリアは登録数が特に多い) プラン料金一覧 ▼エコノミープラン(リーズナブルに利用したい方へ) プラン 料金 内容 壁掛型エアコン 通常タイプ:11,800円 掃除機能付き:17,800円 所要時間:1.0~1.5時間高圧洗浄ファン・フィルター作業場所の養生 天井型エアコン 埋め込み型:22,000円 吊り型:27,500円 所要時間:3.0時間高圧洗浄ファン・フィルター作業場所の養生 エアコン2点セット 単品合計: 28,300 円 セットがお得:23, 900円 エアコン / お風呂 エアコン2点セット 単品合計:28,300 円 セットがお得:23, 900円 エアコン / 換気扇 エアコン3点セット 単品合計:44,800 円 セットがお得:36, 100円 エアコン / 換気扇 / お風呂 エアコン4点セット 単品合計: 61,300 円 セットがお得:49, 200円 エアコン / キッチン / 換気扇 / お風呂 ▼プレミアムプラン(サービス品質を重視したい方へ) プラン 料金 内容 壁掛型エアコン 通常タイプ:15,800円 掃除機能付き:21,800円 所要時間:1.0~1.5時間高圧洗浄ファン・フィルター作業場所の養生 エアコン2点セット 単品合計:36,300円 セットがお得:29,900円 エアコン / お風呂 エアコン2点セット 単品合計:36,300円 セットがお得:29,900円 エアコン / 換気扇 エアコン3点セット 単品合計:56,800円 セットがお得:44,100円 エアコン / 換気扇 / お風呂 エアコン4点セット 単品合計:77,300円 セットがお得:59,200円 エアコン / キッチン / 換気扇 / お風呂 ご利用の流れ STEP 探す カテゴリ(どこをキレイにするか)とお住まいを選択し探しましょう。 作業希望日が決まっている場合は、検索条件を指定して絞り込むのがオススメです。 STEP 注文する 依頼したいプロ(お店)が決まったら注文内容と希望日時を選択します。 「注文に進む」を押下し、新規会員登録を行います。”メールアドレスで登録”または”外部アカウントで登録”いずれかの方法をお選びいただけます。 決済方法は、クレジットカード支払い・楽天ペイ・後払い決済をご用意しています。※サービスによって一部の決済方法がご利用いただけない場合がございます。 内容に問題なければ「注文をする」ボタンを押して、プロ(お店)からの連絡をお待ちください。 サービス提供後、プロから作業完了の報告があがった後に請求処理が実施されます。「ユアマイスター」ではクレジットカードの情報を保存しておらず、安全な決済を行えます。 STEP 注文後 注文後、プロ(お店)からメッセージ機能を通じて、以下の内容等に関して連絡がくる場合があります。 ・訪問日時の調整・機材の型番の確認・駐車場の確認 ご注文後はマイページ上で必ずメッセージをご確認ください。 メッセージ上で訪問日時確定の連絡があれば、そこで注文完了です。 STEP サービスを受ける 注文した日程にて、プロがお伺いします。 作業車の駐車場が確保できない場合、近くのコインパークを使うため駐車場代の実費精算をお願いする場合があります。 提供するサービスによっては洗浄の為ベランダをお借りしたり、水道をお借りする等、ご協力をお願いすることがあります。 詳細についてはプロ(お店)より連絡がありますのでご確認ください。※ハウスクリーニングの一部サービスには、再施工・故障や破損に関する補償をご用意しております。 STEP お支払いする サービス提供後、プロから作業完了の報告があがった後に請求処理が実施されます。 STEP 評価する サービス完了後は、マイページ上でプロ(お店)の口コミを投稿しましょう。 プロ(お店)への励みにもなり、今後のサービス向上にも繋がります。 他のお客様のご検討時にも参考になりますので、ぜひお客様の感想を聞かせてください! クリーンクルーは掃除箇所ごとに自由に組み合わせられるセットプランが充実 クリーンクルーの特徴 掃除箇所ごとに自由に組み合わせられるセットプランが充実 全スタッフが自社研修を受けており、技術力と接客対応に安定感 事前見積もり+後払い制で安心の明朗会計 クリーンクルーは、関東・関西・九州を中心にハウスクリーニングを提供する専門業者です。 特に複数の清掃箇所をまとめて依頼できるセットプランが豊富で、「水まわり4か所セット」や「カビ対策セット」など、目的や生活スタイルに応じた柔軟な選び方が可能です。 この業者の大きな特長は、すべての作業を自社スタッフが対応している点にあります。 事前に技術研修とマナー研修を受けたスタッフのみが現場に派遣されるため、対応の質が安定しており「人によって差がある」といった不安が少ないのが強みです。 また、見積もり時に提示された料金がそのまま適用される「明朗会計制」を導入しており、追加料金の心配がありません。 支払いは作業完了後で、内容を確認してから決済できるため、初めての方でも安心です。 水回りだけでなく、ベランダや窓サッシ、床ワックスなど対応範囲が広い点も、戸建て・マンション問わず高評価を得ている理由のひとつです。 クリーンクルーの公式サイトこちら ユアマイスターのサービス詳細 駐車料金 駐車スペースがない場合は実費請求 キャンセル料 前日までは無料、当日はキャンセル料が発生する可能性あり 土日祝対応 追加料金なしで対応可能 女性スタッフ指名 不可 損害補償 作業中の損害に備えた賠償責任保険に加入 決済方法 現金、銀行振込 対応エリア 関東・関西・九州中心(エリア詳細は公式要確認) プラン料金一覧 ▼おそうじプラン プラン 料金(税込) 所要時間 エアコン洗浄(家庭用壁掛タイプ) 標準価格:13,200円2台目以降:11,550円 2時間 家庭用壁掛タイプ【お掃除機能付き】 標準価格:22,000円2台目以降:20,350円 3時間 家庭用埋込タイプ 標準価格:26,400円2台目以降:24,750円 2時間 家庭用埋込タイプ【お掃除機能付き】 標準価格:31,900円 3時間 業務用エアコン【埋込タイプ/4方向】※正方形吹出口4箇所 標準価格:38,500円 3時間 業務用エアコン【埋込タイプ/1方向】※長方形吹出口1箇所 標準価格:38,500円 3時間 業務用エアコン【埋込タイプ/2方向】※長方形吹出口2箇所 標準価格:38,500円 3時間 業務用エアコン【壁掛タイプ】 標準価格:33,000円 3時間 業務用エアコン【天井吊り下げタイプ】 標準価格:39,600円 3時間 レンジフードのおそうじ 標準価格:17,600円 1~1.5時間 キッチンのおそうじ 標準価格:19,800円 1.5~2時間 浴室のおそうじ 標準価格:19,800円 1.5~2時間 トイレのおそうじ 標準価格:13,200円 0.5~1時間 床(フローリング)のおそうじ 標準価格:13,200円 0.5~1時間 床(フローリング)のワックス剥離 標準価格:22,000円 0.5~1時間 床(フローリング)のワックス 標準価格:16,500円 0.5~1時間 洗面所のおそうじ 標準価格:12,100円 0.5~1時間 窓・サッシのおそうじ(100*180) 標準価格:8,800円 0.5~1時間 窓・サッシのおそうじ(180*180) 標準価格:11,000円 0.5~1時間 ベランダのおそうじ 標準価格:13,200円 0.5~1時間 玄関のおそうじ 標準価格:13,200円 0.5~1時間 車庫・ガレージのおそうじ 標準価格:13,200円 0.5~1時間 定期清掃 標準価格:19,800円 2時間~ 選べるおそうじ 標準価格:20,900円 1時間~ 流れを確認 STEP まずはお問い合わせ お電話(フリーダイヤル:)もしくはお見積もりフォームよりお申し込み下さい。 STEP 訪問見積もりの日程調整 お客様のご要望・ご相談を承り、訪問見積もりの日程調整を行います。 STEP お見積もりのご提出 アドバイザーが訪問してお見積もりを作成。当日or日時を設定し作業します。 STEP 作業開始 ご要望いただいた内容にてお掃除作業を行います。 STEP 作業完了 作業完後お立会い確認いただき、各お支払方法でお支払いいただきます。 ハートクリーニングは防カビ・防臭イオンコーティングが無料 ハートクリーニングの特徴 防カビ・防臭イオンコーティングが無料 高圧洗浄機による徹底的な清掃 豊富なセットプランでコストパフォーマンス良好 ハートクリーニングは、関東・関西・九州エリアを中心に専門性の高いハウスクリーニングサービスを提供している清掃会社です。 特に力を入れているのがエアコンクリーニングで内部のカビや汚れを高圧洗浄で徹底的に除去し、清潔な空気環境を整えます。 同社の大きな特長は、エアコン清掃後に施される「防カビ・防臭イオンコート」が無料であることです。 一般的にはオプション扱いされるこの仕上げが標準で含まれており、清掃の効果を長持ちさせたい方には大きなメリットといえます。 また、複数の箇所をまとめて清掃できるセットプランも人気で水まわり3点セットや5点セットのほか、清掃箇所を自由に選べる「お好み清掃プラン」も用意されています。 予算や住まいの状況に応じて柔軟に選べるため、幅広い世帯に対応できる汎用性の高さも魅力です。 サービスの品質に加え、見積もり前後での対応も丁寧で、初めての利用者でも安心して依頼できる体制が整っています。 プロの技術とコスパのバランスを重視する方にとって、有力な選択肢となるでしょう。 ハートクリーニングの公式サイトはこちら ユアマイスターのサービス詳細 駐車料金 駐車スペースがない場合は実費請求 キャンセル料 作業実施日の3日前まで無料2日前のキャンセルは税込金額の30%、前日のキャンセルは税込金額の50%、当日のキャンセルは100%全額を頂戴いたしております。 土日祝対応 追加料金なしで対応可能 女性スタッフ指名 可 損害補償 あり 決済方法 現金、銀行振込 対応エリア 関東・関西・九州中心(エリア詳細は公式要確認) 料金プラン一覧 ▼エアコンクリーニング エアコンクリーニング壁掛け プラン 料金 時間 範囲 壁掛けエアコン 10,780円※2台目以降、9,680円 1~1.5h エアコン本体/アルミフィン/ファン/外装パネル/フィルター お掃除機能付(一部機種除く) 17,380円 1.5~2h エアコン本体/アルミフィン/ファン/外装パネル/フィルター/お掃除ユニット シャープ機能付・富士通ノクリアXシリーズ・三菱FZシリーズ など 21,780円 2~3h エアコン本体/アルミフィン/ファン/外装パネル/フィルター/お掃除ユニット エアコンクリーニング天井埋込式 プラン 料金 時間 範囲 家庭用埋込式1方向 16,280円 1.5~2h エアコン本体/外装パネル/フィルター/ファン/アルミフィン/ドレンパン 家庭用埋込式2方向 21,780円 1.5~2h エアコン本体/外装パネル/フィルター/ファン/アルミフィン/ドレンパン 業務用埋込天吊1方向・2方向・4方向 27,500円 1.5~2h エアコン本体/外装パネル/フィルター/ファン/アルミフィン/ドレンパン ご利用の流れ STEP まずはお問い合わせ お電話またはWEBで無料お見積り! お電話(フリーダイヤル:0120-970-784)もしくは当サイトよりお申し込み下さい。WEBからお問い合わせいただいた場合は担当スタッフより、折り返しお電話、ご希望の方にはメールにてご連絡いたします。お客様のクリーニング希望箇所、ご希望の日時、詳細をお伺いいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ♪※ご希望の日程は、2・3日ご提示ください。※エアコンクリーニングご希望のお客様は型番が必要になるので事前にご用意いただくとスムーズにご案内できます。 STEP ご訪問日確定 日時・所用時間・料金・サービス内容・お支払方法などの最終お見積りをご確認いただき、相違がなければご訪問日確定! 午前: 9:00-9:30午後: 11:00-14:00 / 13:00-16:00夕方: 15:00-17:30と枠でのご予約になりますので、細かな実際の到着時間は前日にお電話またはメールにてご連絡いたします。※事前入金ご希望のお客様はお申し出くださいませ。 STEP 作業スタート ご依頼いただいた日時に、ハートクリーニングの担当スタッフがお伺いします。 ①お客様にご挨拶の後、作業を始める前に所要時間・料金・サービス内容・動作確認をお客様とご一緒にさせていただきます。②作業終了後、再度ご一緒に仕上がり・動作確認をしていただきます。※作業中は席を外していても問題はありませんが外出される場合には、担当スタッフにご相談お願いします。※作業終了後に万が一、汚れ残り等気になることがある際はスタッフに遠慮なくお申し出くださいませ。 STEP お支払い 当日の清掃終了後、作業スタッフに現金にてお支払いいただきます。 領収証の必要の場合はその際にご指示ください。※クレジットカード、電子マネーの取り扱いはございませんのでご了承ください。 東京のハウスクリーニング業者おすすめ3選【マッチングサイト編】 東京でハウスクリーニング業者を探す際、マッチングサイトを利用すると便利です。 条件で絞り込んでハウスクリーニング業者を比較できるためおすすめです。 ・くらしのマーケット・ミツモア・ユアマイスター 以下で詳細に説明していくので参考にしてみてください。 くらしのマーケット くらしのマーケットのポイント 業者ごとの口コミ・評価を見ながら自分で比較・選択できる 価格設定がわかりやすく低価格帯の業者も多数登録 東京都内の登録事業者数が非常に多く選択肢が豊富 くらしのマーケットは、個人・法人を問わずハウスクリーニング業者を検索・比較できるマッチングサイトです。 東京都内では特に登録業者数が多く、エリアやサービス内容に応じて多様な選択肢の中から最適な業者を探すことができます。 サイト上では、価格や作業内容に加えて、過去の利用者による口コミ・星評価が公開されています。 これにより、価格だけではなく接客態度や作業の丁寧さまで含めた判断ができるようになっています。 料金設定は基本的に業者ごとに異なりますが、全体的にリーズナブルな価格帯が多く、相場より安価に依頼できる業者を見つけやすい点が特徴です。 サイトはスマートフォンにも最適化されており、初めて利用する方でも直感的に操作できる設計となっています。 また、利用者の希望日程や女性スタッフ希望といった条件で絞り込みができるため、ライフスタイルや生活環境に合わせた業者選びがしやすくなっています。 予約から作業完了までの流れがシンプルで、Webに不慣れな人にも使いやすいのが魅力です。 くらしのマーケットを詳しく見る ミツモア ミツモアのポイント 簡単な質問に答えるだけで最適な業者から見積もりが届く やりとりはすべてWeb上で完結し手間が少ない 事前見積もり方式で価格と内容のすり合わせができる ミツモアは、質問に答えるだけで業者から一括で見積もりが届くマッチング型のプラットフォームです。 東京都内でも多くの業者が登録しており、エアコンや水回りのハウスクリーニングを希望するユーザーにとって、スピーディーかつ効率的に業者選定ができる仕組みが整っています。 ユーザーは、掃除したい場所や部屋の広さ希望日時などいくつかの質問に回答するだけで対応可能な業者から直接見積もりが届きます。 価格やサービス内容を比較しながら、自分の条件に合った業者を選べるため初めての利用でも安心感があります。 また、見積もり内容には「作業範囲」や「追加費用の有無」などが明記されており、納得したうえで正式に申し込むことができます。 サイト上でやりとりを完結できるため、電話連絡が不要なのもミツモアならではの利点です。 利用者のレビューも反映されており、実績や対応満足度の高さから業者を選ぶことができます。 ミツモアは、価格と内容のバランスを自分で見極めたい方や、複数の候補から選びたい方に適したサービスです。 東京のような都市部では選択肢も多いため、見積もり結果を比較するだけでも十分に価値があります。 ミツモアを詳しく見る ユアマイスター ユアマイスターのポイント 専門清掃に強い業者が多数登録し対応の幅が広い 「こだわり条件」から絞り込みができる検索性の高さ 定期利用や法人向けプランにも対応できる柔軟な体制 ユアマイスターは、専門性の高い清掃業者や職人が登録しているマッチングプラットフォームです。 東京都内ではエアコンや水回りのクリーニングに限らず、網戸・ベランダ・洗濯機といったニッチな清掃にも対応しており、他のマッチングサイトにはない柔軟な使い方ができます。 特徴的なのは、利用者側の「こだわり条件」での絞り込み機能です。 女性スタッフの対応や営業時間、エコ洗剤使用の有無など、清掃以外の細かなニーズまで加味した業者選びができるため、家庭ごとの事情に合ったサービスを探しやすくなっています。 また、法人向けや定期清掃の依頼もできる点も評価されています。 マンションオーナーや店舗経営者の利用も多く、訪問頻度や作業内容をカスタマイズできる点が支持されています。 都内では共働き世帯や高齢者家庭など、定期的なサポートを求める層にも広く使われています。 予約から支払いまではすべてオンラインで完結でき、やりとりもサイト上で行われます。 口コミ数も豊富で、作業写真とあわせて実際の仕上がりが可視化されているため初めて利用する方でも安心感があります。 ユアマイスターを詳しく見る ハウスクリーニング業者の選び方 ハウスクリーニングでは業者選びが重要です。 業者によって料金やサービス内容が細かく異なるため比較する必要があります。 以下のポイントを比較して自分に合った業者を探してみてください。 東京都ハウスクリーニングの選び方 料金体系と作業内容が明確な業者を選ぶ 口コミや評判をチェックして信頼できる業者を選ぶ 損害賠償保険に加入しているか 女性スタッフの指名ができるか 料金体系と作業内容が明確な業者を選ぶ 料金や作業内容を事前に明確に提示してくれる業者を選ぶことが、後悔しないハウスクリーニングの第一歩です。 なぜなら、料金体系が不透明なまま依頼してしまうと作業当日に追加費用を請求されるなど、思わぬトラブルにつながる可能性があるからです。 明朗な料金表示と、具体的な作業範囲の説明がある業者であればそうしたリスクを未然に防ぐことができます。 特に注意したいのは、同じ「浴室クリーニング」や「エアコン洗浄」という名称でも、分解の有無やオプションの範囲が業者によって大きく異なる点です。 料金が安く見えても、必要な作業が別料金になっているケースは少なくありません。 サービス内容の詳細は、公式サイトや見積もり時の説明で事前にしっかりと確認しましょう。 内訳を提示してくれる業者であれば、初めての方でも安心して依頼できるはずです。 口コミや評判をチェックして信頼できる業者を選ぶ ハウスクリーニング業者を選ぶ際には、実際に利用した人の口コミや評判を必ず確認しましょう。 口コミは、公式サイトや広告では見えにくい実態を知るための重要な判断材料です。 料金の妥当性、作業の丁寧さ接客対応など利用者が体験したリアルな感想は信頼できる業者を見極めるうえで大きな手がかりになります。 ただし、評価が高いからといって無条件に安心するのではなく、投稿数や内容の具体性にも注目することが大切です。 極端に評価が高すぎる場合や、短期間に集中して投稿されているレビューには注意が必要です。 比較サイトやマッチングサービスでは、作業写真や実績件数もあわせて確認できるため、判断材料として活用しやすくなっています。 評価の高い業者であれば、初めての利用でも安心して依頼できるでしょう。 損害賠償保険に加入しているか 業者が損害賠償保険に加入しているかどうかは、依頼前に必ず確認すべきポイントです。 ハウスクリーニングは、一般家庭の設備や家具に直接手を加える作業でありたとえプロの技術であっても、万が一の破損や故障が発生するリスクはゼロではありません。 損害賠償保険に加入している業者であれば、万一の事故にも補償が適用され利用者の負担を避けることができます。 中には保険未加入のまま営業している個人業者も存在しており、事故が起きた際に修理費用を巡ってトラブルになるケースもあります。 契約前に「保険加入の有無」と「補償内容の範囲」は、見積もり時にしっかり確認しておく必要があります。 多くの信頼できる業者では、公式サイトやマッチングページに「保険加入済み」と明記されています。 安心して任せたいなら、補償体制が整っているかをひとつの基準にするのが賢明です。 女性スタッフの指名ができるか ハウスクリーニングを依頼する際は、女性スタッフの指名が可能かどうかも事前に確認しておきましょう。 特に一人暮らしの女性や高齢者のご家庭では、見知らぬ男性スタッフが自宅に入ることに不安を感じる方も少なくありません。 女性スタッフであれば、心理的な抵抗が軽減されるだけでなく、細かな気配りや配慮を期待する声も多くあります。 ただし、女性スタッフを常に配置できる業者は限られており、サービスによっては指名ができない場合や、対応エリアが限定されていることもあります。 申し込みの際に「希望条件」として記入しても、当日になって対応できないケースもあるため注意が必要です。 マッチングサイトや比較サービスの中には「女性スタッフ対応可」の条件で検索できる機能もあります。 安心してサービスを受けたい方は、こうした機能を活用して条件に合う業者を選ぶと良いでしょう。 【間取り・場所別】東京のハウスクリーニング料金相場 東京のハウスクリーニング料金相場を掃除する「場所・部位」「間取り別」で算出しました。 間取りや掃除個所によって料金が大きく変わるので把握しておきましょう。 「場所・部位」 6,000円~18,000円「間取り別」 15,000円~60,000円 ハウスクリーニング業者を選ぶ際は相場より安い業者を選ぶようにしましょう。 掃除する場所・部位ごとの相場比較 ハウスクリーニングを検討する際に気になるのが「どの場所を掃除するといくらかかるのか」という点ではないでしょうか。 掃除の対象となる場所は、水回りやエアコン、窓、床など多岐にわたり、それぞれの料金相場にも違いがあります。 特にキッチンや浴室は汚れが溜まりやすく、自分で落とすのが難しいためプロに依頼する人が多い傾向にあります。 以下の表では、主な掃除箇所ごとの相場をまとめています。 業者によっては、作業内容の詳細やオプション(防カビ加工・分解洗浄など)によって価格が変動するため、目安として参考にしてください。 掃除箇所 相場価格(目安) キッチン 12,000〜18,000円 換気扇・レンジフード 8,000〜15,000円 浴室(バスルーム) 13,000〜20,000円 トイレ 7,000〜10,000円 洗面所 6,000〜10,000円 エアコン(壁掛け) 9,000〜13,000円 間取り別の相場比較 掃除を依頼する際は、部屋の「間取り」によっても料金が変わります。 間取りが広くなるほど清掃箇所が増えるため、所要時間や人員も多くなり当然ながら費用も上がっていきます。 ただし、広い物件でもまとめて依頼することで割安になる「パックプラン」などを用意している業者もあるため、事前の見積もり確認が大切です。 以下に、一般的な間取りごとの相場を掲載しました。 掃除範囲(キッチン・浴室・トイレ・窓など)を含んだパッケージ価格の目安となっています。 間取り 相場価格(目安) 1R / 1K 15,000〜25,000円 1DK / 1LDK 20,000〜35,000円 2LDK / 3LDK 30,000〜60,000円前後 築年数や汚れ具合、家具の有無によって価格が上下するケースもあります。 より正確な費用を知りたい方は、無料の現地見積もりを依頼するのがおすすめです。 複数社で比較すれば、自分に合ったプランが見つけやすくなりますよ。 ハウスクリーニングよくあるQ&A 最後にハウスクリーニングでよくある質問をご紹介します。 よくある質問 ハウスクリーニング費用以外にかかる料金はある? ハウスクリーニング業者を呼ぶときは家にいるべき? 悪質なハウスクリーニング業者の見分け方は? 業者が訪問する当日に準備しておくことは? ハウスクリーニング費用以外にかかる料金はある? 基本料金に含まれない追加費用が発生する場合もあります。 たとえば、駐車場代や特殊な汚れへの対応費、オプション追加などがその一例です。 駐車場がない場合は、近隣のコインパーキング代を実費請求されることがあります。 また、カビや油汚れがひどい場合には作業時間の延長や専用薬剤の使用により追加費がかかるケースも見受けられます。 その他、土日祝日の対応や、女性スタッフの指名、早朝・夜間帯の作業などで追加料金が設定されている業者もあります。 申し込み前に「基本料金に含まれる作業内容」と「追加費用が発生する条件」を確認しておくと、当日のトラブルを防ぐことができます。 ハウスクリーニング業者を呼ぶときは家にいるべき? 基本的には在宅が望ましいですが、不在対応が可能な業者もあります。 初回利用や細かい指示が必要なケースでは、立ち会いがあることで誤解やミスを防ぎやすくなります。 特に浴室やキッチンなどの水回り清掃では、掃除してほしい箇所や触れてほしくない物の事前説明が重要です。 ただし、日中に立ち会えない人向けに、不在時対応や鍵預かりサービスを提供している業者も増えています。 セキュリティ面の不安がある場合は、プライバシー管理や損害補償制度が整っているかを確認しましょう。 在宅・不在のいずれにしても、作業前の打ち合わせと作業完了後の報告がしっかりしている業者であれば安心して依頼できます。 自分の生活スタイルに合った対応方法を選ぶのがポイントです。 悪質なハウスクリーニング業者の見分け方は? 料金やサービス内容が不透明な業者には注意が必要です。 トラブルが多い業者に共通して見られるのは、料金の詳細をあいまいにしたまま契約を進めるケースです。 見積もりなしで作業に入り、終了後に高額な追加料金を請求されたという事例も少なくありません。 また、「キャンペーン中」と強調しながら契約を急がせたり、「今日中に申し込めば割引」といったセールストークで判断を急がせる業者にも注意が必要です。 公式サイトに会社概要やサービス詳細、損害補償制度などの記載がない場合も、信頼性に疑問が残ります。 事前に口コミやレビューを確認し、複数社で相見積もりを取ることが予防策になります。 また、マッチングサイトを利用すれば、実績や評価が明確な業者を選ぶことができるため、初めての方にはおすすめです。 業者が訪問する当日に準備しておくことは? 貴重品の管理と作業スペースの確保をしておくのが基本です。 ハウスクリーニングでは、作業する部屋や設備の周辺にある私物をあらかじめ片付けておくことで、清掃がスムーズに進みます。 特にキッチンや浴室などは、掃除道具や洗剤を広げるスペースが必要になるため洗面用具や食器類をあらかじめ移動させておくのが望ましいです。 また、業者によっては電源や水道を使うこともあるため、該当設備の使用が可能な状態にしておくとよいでしょう。 ベランダやエアコン周辺など、屋外作業がある場合は洗濯物を干していないかも確認しておくと安心です。 さらに、貴重品や壊れやすいものは事前に自分で保管しておくことが基本的なマナーです。 不在での作業を依頼する場合には、鍵の受け渡し方法や作業終了後の報告方法も確認しておくとトラブル防止につながります。 東京のハウスクリーニングは料金体系が明瞭な信頼できる業者を選ぶことが大切! ハウスクリーニングとは、専門業者が住宅内の汚れやカビ・ホコリなどを徹底的に清掃してくれるサービスです。 東京でハウスクリーニングを検討中の方は料金体系が明確な業者を選ぶことが大切です。 ハウスクリーニングの最終料金は、作業範囲や作業時間、汚れの程度などで決定します。 想像を超える金額にならないよう事前に見積もりをしておくようにしましょう。 また、口コミや評判をチェックして信頼できる業者であるかを確認することも大切です。 東京都ハウスクリーニングの選び方 料金体系と作業内容が明確な業者を選ぶ 口コミや評判をチェックして信頼できる業者を選ぶ 損害賠償保険に加入しているか 女性スタッフの指名ができるか 料金体系を確認の上、自分に合ったサービスを選ぶことで日々の日常を合理的かつ効率的な暮らしにすることができます。
記事を読む

2024.04.02コラム
東京で3年ぶり「はしか(麻しん)」の感染報告
世界各地で流行中の「はしか」の正しい知識と予防策
今年に入り、東京や大阪をはじめとして、国内で「はしか(麻しん)」の感染報告が確認されています。感染者は海外で感染したとみられており、海外から観光旅行で日本に来た人や海外へ出張や旅行に行った人が日本に帰ってきてから、感染が確認されています。日本は、平成22年(2010年)11月以降の「はしか(麻しん)」のウイルス分離・検出状況については、海外由来型のみ確認されており、平成27年(2015年)3月27日、世界保健機関西太平洋地域事務局により、日本が麻しんの排除状態にあることが認定されています。厚生労働省は「仕事や旅行で海外に行く人などはワクチンの接種歴や抗体の状況を確認したり、必要に応じてワクチンの接種を検討してほしい」と呼びかけています。 厚生労働省WEB「麻しんについて」より 今回のDELMAGAは、感染症・疫学がご専門の防衛医科大学校の加來先生に監修いただきながら、「はしか(麻しん)」の特徴、症状、感染経路、予防策などの情報をお届けしていきたいと思います。最後までお付き合いください。 国内における「はしか(麻しん)」の感染状況日本は2015年にWHO(世界保健機関)より『麻疹排除状態にある』と認定を受けています。排除達成後も海外からの旅行者を発端とした集団発生、医療機関における集団発生、ワクチン接種率が低い集団における集団発生などがあり、2019年の感染報告数は排除達成後最多の744例となりましたが、2020年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに伴う国内外の人の往来制限などの影響もあり、年間届出数は2020年:10例、2021年:6例、2022年:6例となり、人の往来が戻り始めた2023年は28例でした。日本においては、今後も海外からの旅行者がさらに増えていく中で、海外からの麻しん持ち込みのリスクもより高まることが予想されます。今年に入ってから2024年は第6週(2月5日~11日)までは、「はしか(麻しん)」の国内での発生はありませんでしたが、第7週(2月12日~18日)に東京都内での1名の発生を皮切りに、各地で散発的に発生がみられるようになりました。これは海外で感染し国内で発症する「輸入事例」が起点となったものです。いくつか例をあげますと、まずは奈良県での事例です。2月23日に奈良市ではじめて麻疹の届け出がありました。その後、3月6日にこの患者の接触とされた方からの発生がみられました。1人目は外国人旅行者の男性(20代)で2月7日に日本に入国し、その後、奈良市内に滞在中の2月19日に発症。2人目は旅行者の接触があったとされる男性(30代)で3月6日に「はしか(麻しん)」と診断されました。二つ目は大阪府での事例です。2月29日に東大阪市で男性(20代)の感染が報告されました。この男性は昨年からアジアや中東を旅行し、2月24日にアブダビ発の航空機で関西空港に帰着。航空機に同乗していた乗客8人が相次いで「はしか(麻しん)」と診断されました。 NHK WEB「はしか感染者相次ぐ 空気感染も ワクチン接種が必要な世代は…」 都内でも感染報告さきほどの二つ目の報告にある感染者と航空機で同乗していた8人のうち大阪市の女性(20代)は滞在先の東京で発症し、都内医療機関を受診して麻疹の感染が確認。東京都は、女性が利用した新幹線や飲食店の具体的な情報を公開し、同じ場所にいた人に対し、体調に異変があった場合は事前に連絡したうえで公共交通機関を使わずに医療機関を受診するよう呼びかけました。これは、感染拡大を防ぐために、曝露された方に対する注意喚起を促して、早期発見・治療に結び付けるために行われたものです。【東京都による報道発表】女性(20代)は・3月7日(木)午後1時45分大阪駅発東海道新幹線のぞみ24号の6号車に乗車し、午後4時8分に品川駅に到着し下車。・同日、午後9時から午後11時ごろまで、都内の●●● 銀座コリドー通り店に滞在。※お店●●●へのお問い合わせはご遠慮ください。 「はしか(麻しん)」は感染力が強く、特効薬がない「はしか(麻しん)」は、・麻しんウイルスによる発熱性、発疹性の感染症・感染経路は、主に空気感染(感染したヒトの呼気中に含まれる空気を吸い込んで感染)・潜伏期間は、通常は10日~12日(早い人で7日から遅い人で21日に発病することもあります。)・免疫を有さない人に対しては、感染力が非常につよい。・免疫を有さない人が感染すると、ほぼ間違いなく症状が出るが、ワクチン接種歴が1回の人が感染すると症状がわかりにくい麻疹(修飾麻疹)を発症する。・特効薬はなく、治療は基本的に対処療法(病気の症状をやわらげる)・合併症により生死にかかわることがある改めて、「はしか(麻しん)」についての情報をまとめます。症状は、発熱、咳・鼻水、全身の発疹感染後10~12日ぐらいで発症することが多く、38度以上の発熱が2~4日程度続き、咳・鼻水などの気道症状、結膜炎(目の充血、目やに・涙)などが現れ次第に症状が強くなります。これをカタル症状といいます。乳幼児では下痢や腹痛を伴うことがあります。口内の頬粘膜にできる白い斑点(コプリック斑)や全身に発疹が出ます。一度発熱が下がりかけた後に、再び高熱(39.5度以上になることが多い)が3~4日続き、はしか(麻しん)特有の赤い発疹が出ます。発疹は顔面から出始め、身体全体に広がっていき、その後褐色の色素沈着がしばらく残ります。通常であれば、7~10日間程度で症状は徐々に回復します。合併症として、肺炎、脳炎、中耳炎、クループ(のどの奥が感染により腫れてしまうことで、声がかすれたり、息を吸うときにヒューヒューと音がしたりすること)などがあります。重症な肺炎では、呼吸困難で集中治療室に入院したり、発症1,000人に1~2人の頻度で生じる急性脳炎では、生命に危険が及んだり後遺症を残すこともあります。幼児、免疫不全などの基礎疾患のあるお子さん、妊婦さんは重症化に注意が必要です。妊婦さんが感染すると、重症化だけではなく、流産や早産を起こす可能性もあります。 感染経路は「空気感染」はしか(麻しん)の感染経路は、「接触感染」「飛沫感染」だけでなく、「空気感染」でも感染が拡大していきます。接触感染:ウイルスが付着した手を介して感染が広がる飛沫感染:咳やくしゃみで飛散したウイルスを含む飛沫で感染が広がる空気感染:呼吸により飛散し、空間を漂うウイルスで感染が広がる「空気感染」は、集団の場で1人の発症があった場合、同じ空間にいる人は、感染してしまう可能性があります。麻疹ウイルスは、浮遊中や付着した物質の表面上で最大2時間の活性があると言われており、その間2時間は感染力を持つといえます。はしか(麻しん)は非常に感染力が強く、免疫のない人が感染すると、ほぼ100%近くの人が発症すると言われています。また感染者1人が免疫を有さない人に何人にうつすかを示す「基本再生産数(R0)」は、12~18人になります。(参考:インフルエンザでは1~2人、COVID-19では2~3人)発症した患者さんでは、発熱の1日前の無症状期から、すなわち発疹の出る4日前からで感染力があると言われていますので、早期発見と対策を行わないと感染拡大が起こってしまいます。 対策はワクチン接種麻しんは空気感染もするので、手洗い・マスクのみで予防が難しく、最も有効な予防法はワクチン接種になります。麻しんの患者さんに接触した場合でも、72時間以内に麻しんワクチンの接種をすれば発症を予防できるとされていますが、現実的な方法ではありません。やはり事前にしっかりと2回接種しておくことが重要です。ワクチンの有効性は、インフルエンザワクチンやCOVID-19ワクチンと異なり、感染予防効果が非常に高いです。現在、国内では生後1歳を過ぎた段階で1回目、小学校に入学する前に2回目のワクチンを接種することが定期接種として推奨されています。というのもワクチン1回接種による免疫獲得率は93~95%以上ですが、時間の経過とともにその効果が薄れてしまいます。そこで2回目の接種を行い、免疫獲得率を97~99%以上に高めるという作戦です。初回接種後の反応としては発熱が約20~30%、発疹は約10%に認められますが、いずれも軽症であり、ほとんどの症状は自然に消失します。 このワクチンの2回接種による定期接種が開始されたのは2006年からですので、年代によって接種回数が1回の人がいます。ワクチンの接種歴は母子手帳などで調べられます。一度,麻しんにかかった人は、強い免疫がのこるため接種は必要ありませんが、症状の程度は個人により異なるので検査を行って麻しん抗体価があるかを確認することが重要です。お子さまのワクチン接種は、小学校入学前に2回2006年4月1日以降、麻疹・風疹混合生ワクチン (measles-rubella:MRワクチン)の定期の予防接種が始まり、 2006年6月2日から下記の年齢での2回接種となりました。第1期、第2期を過ぎてしまうと定期の予防接種として受けられなくなってしまいます。 お子さまの小学校の入学前までに2回目のワクチン接種がすんでいるかを確認し、第2期でまだ麻疹と風疹の予防接種をそれぞれ2回ずつ受けていないお子さまは、 かかりつけ医やお近くの医療機関にご相談ください。接種医療機関は、お住まいの市町村(特別区)にお問い合わせください。 国立感染症研究所 「小学校入学準備に 2回目の麻疹・風疹ワクチンを!」 症状がある場合かかりつけ医や医療機関に電話などで「はしま(麻しん)の疑い」があることや「症状」を伝えて、以降は医療機関の指示に従ってください。医療機関への移動は、公共交通機関の利用は可能な限り避けてください。 参考URL・厚生労働省 麻しんについてhttps://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/measles/index.html ・国立成育医療研究センター はしか(麻疹ウイルス感染症)にご注意ください。https://www.ncchd.go.jp/center/pr/info/0526.html ・国立感染症研究所 麻疹とはhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles.html ・国立感染症研究所 小学校入学準備に 2回目の麻疹・風疹ワクチンを!https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles/221-infectious-diseases/disease-based/ma/measles/590-cpn08.html ・東洋経済 ON LINE 東京でも感染者が見つかった「はしか」どう防ぐ?https://toyokeizai.net/articles/-/740960 ・Forbes 世界的流行のはしか、自分と周囲を守るために知っておくことhttps://forbesjapan.com/articles/detail/69685 ・FNプライムオンライン感染力極めて高い“はしか”都内で確認…東海道新幹線乗り銀座で飲食も 3月にUAEから帰国https://www.fnn.jp/articles/-/669693 ・東京都 報道発表資料 保健医療局 「麻しん(はしか)患者の発生について」https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/03/12/07.html
記事を読む
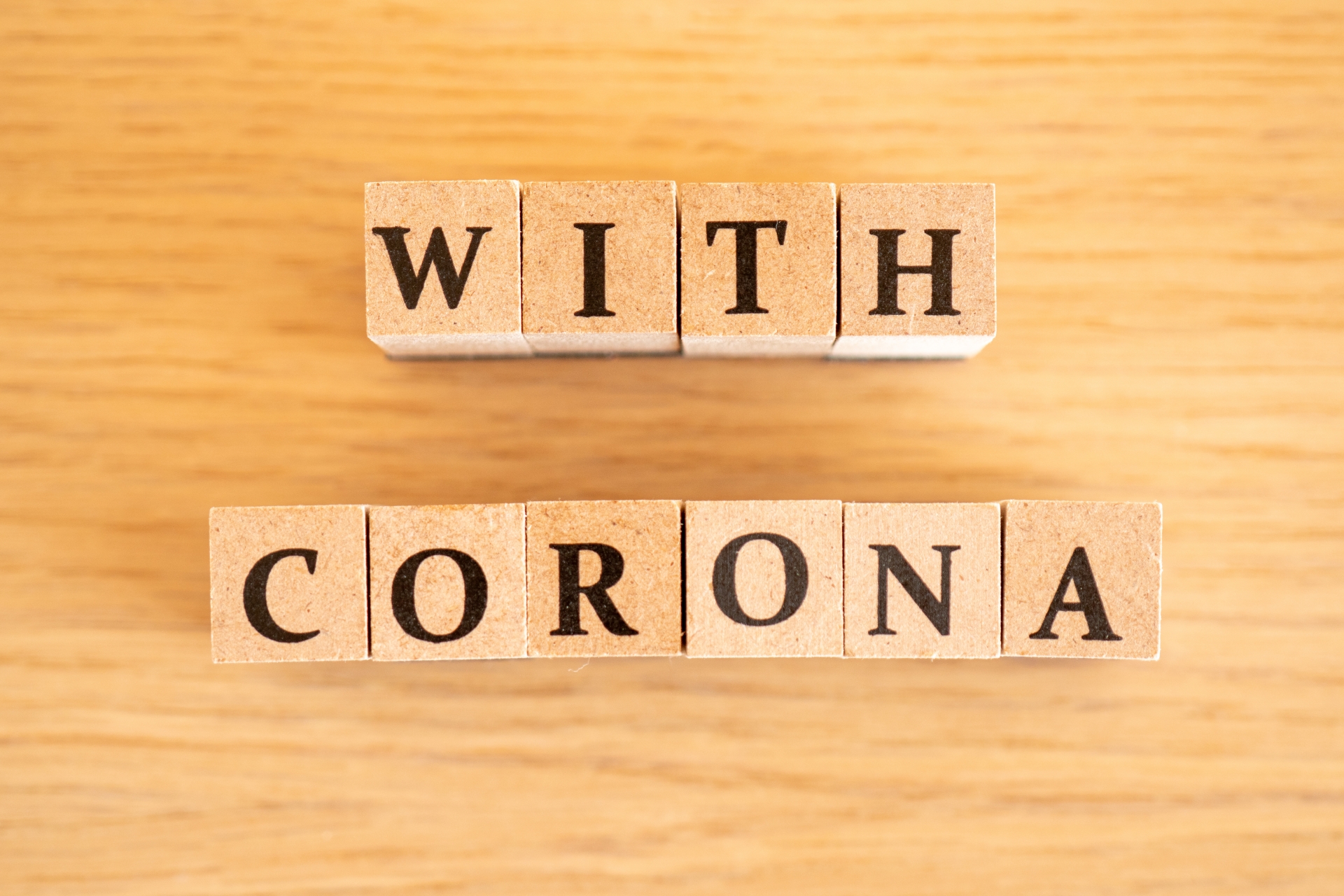
2024.02.19コラム
患者数11週連続増加、どうする!?「コロナとの共生」!
新型コロナウイルス感染症は、感染症法上での位置づけが2023年(令和5年)5月8日に「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる二類相当)」から「五類感染症」になりました。昨年8月から始まった「第9波」の流行が底をうったのが11月中旬です。しかし11月下旬から再び感染報告数が増え始め、DELMAGAを書いている時点での最新の速報値(2/13発表)によると、2月4日の週までに、11週連続で感染報告数が増加しており、「第10波」の真っ最中です。 今回のDELMAGAは、感染症・疫学がご専門の防衛医科大学校の加來先生に監修いただきながら、現在流行している新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の特徴などを分かり易く整理し、改めて注意しておきたい情報をお届けしていきたいと思います。最後までお付き合いください。 11週連続で感染報告増加現在コロナウイルスの流行状況は、週1回、全国の約5,000の医療機関から新規感染者数を報告してもらう「定点把握」となっており、2024年1月29日~2月4日の定点あたりの平均患者数は16.15人となっていますが、これはその前の週(1月22日~1月29日)の14.93人に比べると増加傾向となっています。都道府県別にみると石川県の24.52人が一番多く、福島県24.49人、愛知県22.55人、茨城県22.46人と続いていますが、47都道府県のなかで前週から減っているのは山口県、徳島県、富山県、埼玉県、栃木県、岩手県の6県にとどまっているという状況です。年齢群でみると10歳未満が最も多く、定点当たり4.69、次いで10~14歳が2.51ですが、60歳以上の高齢者では1.00を下回っています。一方で入院患者の届出数は、全国で3,400名前後となっており60歳代311名、70歳代843名、80歳以上1,639名となっており、あわせると全体の80%となっています。 厚生労働省は、冬の流行拡大に注意を呼び掛けており、現在のコロナウイルスの流行状況については「特に若い年代で感染者の増加が目立っている。冬休みが終わり、学校が再開したことも要因として考えれるので、学校での感染対策などを引き続き徹底して欲しい」としています。また、今シーズンはインフルエンザの同時流行が起こっています。インフルエンザA(H1N1株、H3N2株)に加えて、インフルエンザBの流行が確認されています。また、鼻水や鼻づまりなどの症状を主とする花粉症も増え始めています。よく似た症状の患者が増えていることから、医療の現場でも交雑を防ぐなどの工夫が続けられています。 コロナウイルスのいま、これからコロナウイルスによるパンデミック以降、国内ではアルファ、デルタなど変異株が猛威を振るっていましたが、いま国内で流行している主流は、民間検査機関からの検体に基づく情報では「オミクロン株の亜種BA.2系統のJN.1が31.5%、JN.1.4 が14.2%、XBBの一種であるHK.3が10.7%」となっており、明らかに世代交代が起こってきていますこのJN.1は、WHOも「注目すべき変異株」に分類しているウイルス株です。JN.1は「免疫逃避」という一度できた抗体をすり抜ける能力が増しており、2度3度と感染してしまう可能性があります。また、ヒトからヒトへの感染力も高くなっていると言われていますが、重症化は従来のXBB株と変わらないと報告されています。 わたしたちにできることパンデミック時の緊急事態宣言下においては政府の専門家会議より「新しい生活様式」という方針が打ち出されましたが、現在はコロナウイルス感染症が五類感染症となり、わたしたちを取り巻く状況も変わっています。ただし、感染症対策の基本は大きくは変わりません。誰にでも感染してしまう可能性はあり、誰にでも周りにうつしてしまう可能性があります。可能性を意識して、思い込みではない正しい知識をもとに自分でできる行動があります。 <わたしたちにできる基本的な5つの感染症対策>(1) 体調不安や症状があるときは自宅で療養するか医療機関を受診する(2) その場に応じたマスクの着用と症状がある場合の咳エチケット(3) 3蜜(密閉、密集、密接)対策と空間の換気(4) 手洗いの励行(5) 適切な運動、睡眠、食事 (1)体調不安や症状があるときは自宅で療養するか医療機関を受診する体調不良や発熱などの症状がある場合には、無理せずに自宅で療養してください。早めに市販薬で症状を緩和させることも重要ですが、基礎疾患をお持ちの方はぜひ医療機関を受診して、きちんと診察を受けてください。過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう可能性があります。 (2)その場に応じたマスクの着用と症状がある場合の咳エチケット新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどの流行期に自身が罹患しないために、・通勤ラッシュ時などの混雑した電車やバスに乗るとき・何らかの呼吸器症状のある人のお世話をしたり、面会したりするときなどはマスクの着用が効果的です。 自身が知らないうちに広げないために、・咳やくしゃみなどの症状があるときは、マスクを装着します。 これは咳エチケットとしてのマスク装着です。・医療機関の受診時や高齢者施設などを訪問するときも、マスクを装着します。 新型コロナウイルス感染症が無症状の感染期にも人への感染力があるからです。・高齢者、持病のある人、妊婦さんなどと会うときは、自身の体調管理を厳重に行ってください。 大切な人を守るためです。ただし、マスクの着用については、五類移行前の令和5年3月13日より、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう配慮が必要です。上記の基準を参考にして、皆さん自らが正しい判断をされるのを期待いたします。 (3)3蜜(密閉、密集、密接)対策と空間の換気飛沫感染やエアロゾル感染のリスクを下げる方法として、3蜜対策は基本となります。その中で換気が可能であればすぐにでも取り入れてください。こまめに窓を開けて行う自然換気も効果的です。どうしても換気ができないような部屋については、空気清浄機を利用することをおすすめします。 (4)手洗いの励行手洗い、手指消毒は感染対策の「基本のキ」です。五類以降は、社会全体であまり重視されていない傾向があるようなので心配しています。接触予防のための対策としては、きわめて有効ですので、“コロナで学んだこと”の一つとして継続してください。 (5)適度な運動、睡眠、食事感染症対策に限ったことではありませんが、健康維持のため、適度な運動、睡眠、食事はとても重要です。リモートワークの広がりにより在宅で過ごす方も増えましたが、日常的にバランスの良い食事を摂り、適度な運動を行い、ぐっすり睡眠をとりましょう。 お子さまが感染してしまったら感染対策に注意をしていても感染してしまうことがあります。お子様さまコロナウイルスに感染してしまった時のポイントをまとめます。【お子さま(コロナウイルスに感染された方)】お子様は、大人に比べてさまざまな呼吸器感染症に罹患してしまいます。症状からは判断できないことが多いので、かかりつけの医療機関を受診させてください。何らかの症状があるうちは、ウイルスを排出しているものと考えて、家庭内での二次的な広がりに注意してください。 【お世話をする方や同居家族について】まずは、ご自身の体調に注意してください。・感染した家族の方が、ウイルスを排出させなくなるまで(おおむね発症後5日程度)の間は、家庭内で感染するリスクがあります。タオルの共有を避けて、寝室や食事をとる場所を分けるようにしてください。・外出するときには人混みを避け、マスクの着用をおすすめします。高齢者等のハイリスク者との接触を控えるなど、周りの方へうつさないように配慮してください。 <お子さまの観察ポイント>機嫌、食欲、呼吸のようすなどを観察してください。機嫌がよく、食欲があり、顔色が普通であれば基本的に心配いりません。慌てずに様子を見たうえで、かかりつけ医にご相談ください。受診を迷った場合、夜間や休日の場合は電話相談窓口(「救急車利用マニュアル」、「こどもの救急」等関係ウェブサイトの参照や「#7119(救急要請相談)」、「#8000(こども医療相談)」など)をご利用してください。 <家庭できる感染対策>1.こまめに換気をする 共用スペースや他の部屋も頻繁に換気をします。窓を開けて行う自然換気が最も推奨されますが、閉鎖空間の場合には空気清浄機などを利用してください。 2.可能な範囲で部屋を分けるお世話(看病)する方はできるだけ限定して行い、接触する時間をなるべく短くします。ただ、子どもは自らの体調管理や体調不良の意思表示が十分にできないことがあるので、健康状態のチェックを入念に行います。 3.可能な範囲でマスクをするお子さま本人を含めて、同居家族全員はできるだけマスク着用します。ただし、乳幼児(小学校に上がる前まで)のマスク着用には注意が必要で、特に2歳未満のお子さまへのマスク着用はやめましょう。 4.こまめに手洗いをする目に見えて汚れが付いた場合には、石けんで洗い落としますが、そうでなければ(食事の出し入れでお子さんの部屋から出た後など)は、アルコール製剤やそれに類似の手指消毒薬を使用してください。 5.汚れたリネン、洋服は洗濯し、ゴミは密閉して捨てるさいごに令和5年5月8日にコロナウイルス感染症の分類が二類感染症から五類感染症になり、季節性インフルエンザなどと同じ分類になりました。パンデミックや緊急事態宣言などの重々しい社会の雰囲気から「コロナとの共生」に向けて、日常生活や経済活動が動き出しています。五類になったとはいえ、コロナウイルスの性質や感染症の特徴が大きく変わったわけではありません。2024年に入り、いまは「第10波」とも「冬の波」ともいわれています。「自分は大丈夫(かからない)」とか、「前回コロナにかかったが、そんなに(症状が)つらくなかった」など声を聞くことがあります。自分は大丈夫または症状が弱かったとしても、周りにいる大切な誰かに感染症をうつしてしまう可能性もあります。そして、その大切な誰かが、またその周りにいる他の大切な誰かに感染症をうつしてしまうという…というスパイラルも考えられます。基本的な感染症対策は、いまできる対策や簡単にできる対策です。ご自身のため、周りの方のため、改めて再認識していただければとの思いの中、今回のテーマを取り上げました。 参考URL・国立感染症研究所 IDWR速報データ 2024年第5週https://www.niid.go.jp/niid/ja/data.html ・科学技術振興機構 「サイエンスポータル」サイエンスクリップhttps://scienceportal.jst.go.jp/gateway/clip/20240124_g01/ ・厚生労働省 感染対策・健康や医療の相談情報https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1 ・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の五類感染症移行後の対応についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html ・厚生労働省 新型コロナウイルス感染症(変異株)への対応https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000922185.pdf ・東京都医学総合研究所 新型コロナウイルスや医学・生命科学全般に関する最新情報https://www.igakuken.or.jp/r-info/covid-19-info198.html ・NHK 「NEWS WEB」新型コロナ、インフルエンザいずれも患者数増加 対策徹底をhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20240202/k10014344831000.html
記事を読む

2024.02.09介護福祉施設導入事例
やさしさに包まれる住まいを快適に
導入事例:介護複合施設とうふう苑様 「感染ゼロ」をめざし、抗菌・抗ウイルス製品「delfino(デルフィーノ)」を展開する株式会社デルフィーノケア(東京都目黒区)は、2023年9月13日、介護複合施設とうふう苑様に「delfino施設まるごと抗菌」を導入いただきました。 ◇◇複合介護施設とうふう苑様とは介護複合施設とうふう苑様は、ご入居される方にとってこれまでの暮らしの延長上にある「家」であり、「施設に入る」のではなく「人生を愉しむ」空間である、というコンセプトのもと、2018年にオープンされた介護複合施設です。地元である京都府産木材を活用した「木造建築」にこだわり、木の温もりが「対話」を生み、木の香りが「落ち着いた心」で過ごせる空間を演出します。ご入居者、利用者だけでなく、働くスタッフの方々も優しい気持ちで過ごせる家で四季を感じ、生活ができる環境作りをしています。 ◇◇デルフィーノによる施工デルフィーノの「まるごと抗菌」施工を導入いただいた背景として、ご入居様が入れ替わられる際、前入居者様の生活されていた臭いを、新しい入居様がご入居されるまでにクリアな状態にしてご提供したいというご要望がありました。事前の現地調査とスタッフの方へのヒアリングにより、臭いの発生元となっているポイントが床とトイレである可能性が高いと特定して、ポイントごとに清掃状況や消臭効果を確認しながら手作業で行い、防臭効果もあるデルフィーノ「まるごと抗菌」施工を実施しました。今回は、施工後、より消臭防臭効果を高めるため、デルフィーノコーティングと相乗的な効果が見込めるオゾン発生器も室内に設置させていただきました。 ◇◇施工風景噴霧前の清掃①(埃など目に見える汚れの清掃) 噴霧前の清掃②(床は手作業で拭きあげ) 噴霧前の清掃③(トイレも手作業で入念に)専用噴霧器によるコーティング風景①(居住空間)専用噴霧器によるコーティング風景②(トイレ)専用ガンスプレーによる重点コーティング①(ベッド)専用ガンスプレーによる重点コーティング②(トイレ) ◇◇お客様の声(代表取締役 山田幸裕様)ご入居様とそのご家族、ご利用者様、スタッフが快適で過ごすことができる空間・環境を提供するために、常に様々な対策を取っておりますが、ご入居者様の入れ替わりのタイミングの「生活されていた臭い」の課題においては、対策に万全を尽くすものの、対応が難しいときがありました。デルフィーノの施工後、今まで取れなかった臭いが元の状態に戻ったかのように快適な空間となり、職員一同驚いています。もちろん、臭いの効果だけでなく感染症の予防にもつながるため、今回デルフィーノケアさんに依頼して「まるごと抗菌」施工したことを大変喜んでいます。 実施概要導入先 :介護複合施設とうふう苑様代理店 :株式会社Catalyx施設種別:介護施設実施目的:感染症対策、消臭対策実施内容:delfino施設まるごと抗菌 「delfino施設まるごと抗菌」とは 感染症対策製品「delfino(デルフィーノ)」は、「感染ゼロをめざして」というコンセプトのもと、光触媒(酸化チタン)、抗菌触媒(銀)、三元触媒(プラチナ)などの触媒を組み合わせることで、それぞれの触媒反応が持つ効果を相乗的に発揮させながら、それぞれの弱点を補うという発想の抗ウイルス・抗菌・防臭剤です。専用噴霧器によって、デルフィーノをμ(ミクロン)単位の粒子で噴霧、密閉空間に充満させていくことで、壁面だけでなく、カウンター、チェア、デスク、キャビネットなどのあらゆるものを抗ウイルス・抗菌コーティングして、施設内での感染リスクを軽減します。お問い合わせは以下のリンクから。 お問い合わせ
記事を読む
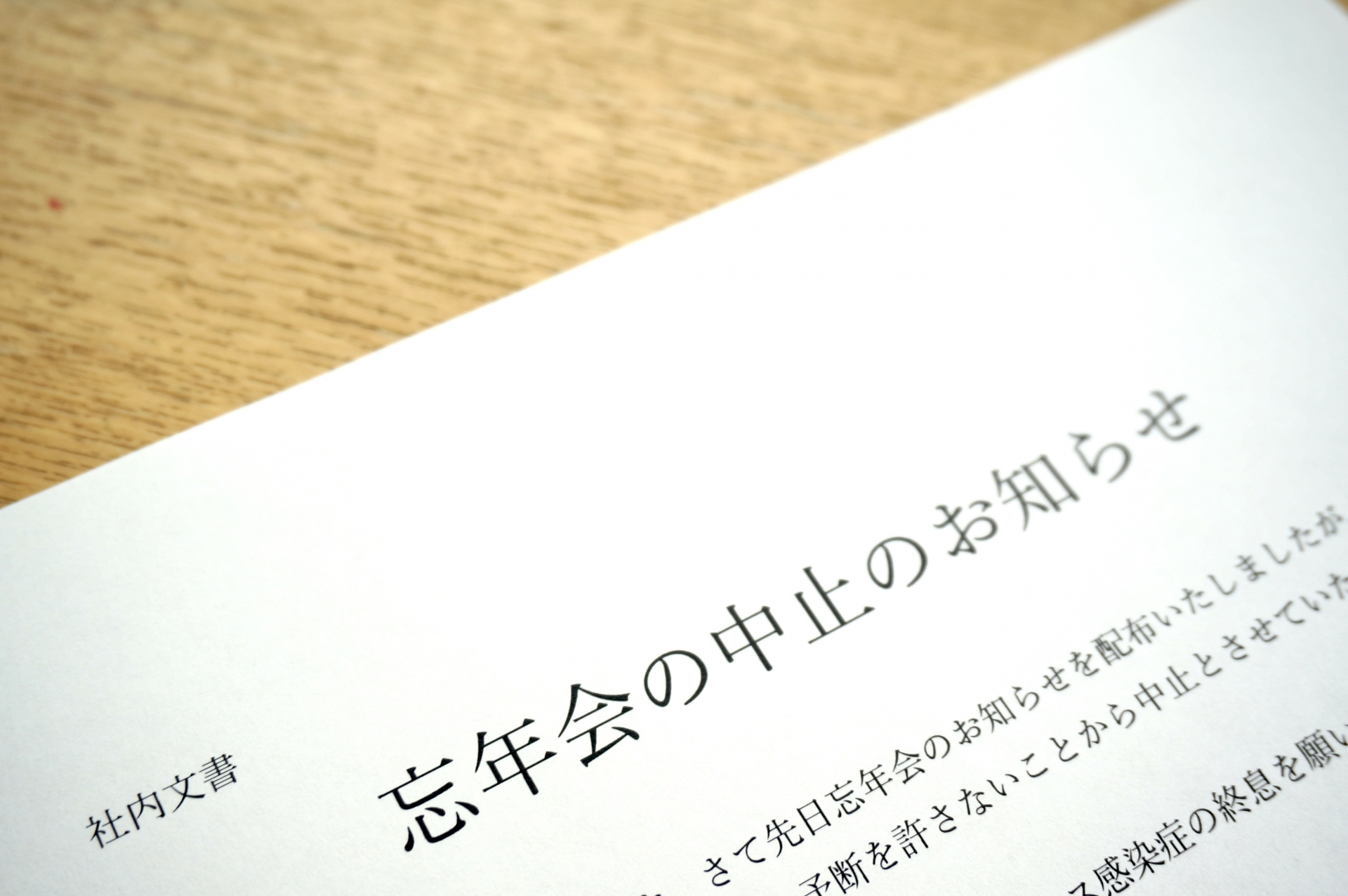
2023.11.28コラム
あなたのまわりにも!?
患者数増!インフルエンザ流行、感染ピークは年末に??
例年11月~12月ごろに流行が始まり、年が明けて1月からピークを迎える冬の感染症のイメージが強いインフルエンザ。 しかしながら、今年は9月から流行の拡大が始まり、厚生9月時点での労働省の発表(9/22発表)では、東京都を含む7つの自治体で注意報レベルに達しているとの発表がありました。東京都においては1999年の統計開始以来、最も早い9月21日にインフルエンザの注意報が出ています。 今回も、感染症・疫学の権威である防衛医科大学校の加來先生に監修いただき、季節性インフルエンザの特徴や注意点などを分かり易く整理しながら、インフルエンザの基礎情報をお届けしていきたいと思います。最後までお付き合いください。 インフルエンザを知ろうインフルエンザとは インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる「急性呼吸器感染症(急な発熱を伴う風邪のような症状が出る感染症)」で、インフルエンザウイルスが喉、気管支、肺で感染し、増殖することにより症状があらわれます。 インフルエンザはどうやってうつる?(感染経路) インフルエンザの感染経路は主に2つあります。 インフルエンザは、ウイルスが手に付着しただけで感染することはありません。ウイルスが付着した手で、口や鼻、目などの粘膜を触れることで感染します。 注1)「感染」とは、インフルエンザウイルスが標的となる細胞の中入ること。 注2)「発症(発病)」とは、なんらかの症状が出ること。 「感染」しても症状が出ないという場合もあります。これを「不顕性感染」といいます。 どんな症状がでるの?(主な症状) 突然の発熱(38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが現れ、次に咳、鼻みず、咽頭痛などの上気道症状が続き、約1週間でおさまります。 主な合併症として肺炎、脳症などがあります。 インフルエンザにかかったら インフルエンザウイルスは体内で感染後、増殖のスピードが速く、発熱(高熱)などの症状が急激に進みます。特にインフルエンザが流行している時期に発熱、咳、のどの痛み、倦怠感、頭痛、鼻みず・鼻づまりなどの症状が出たときは、早めに医療機関での受診を心掛けてください。 持病がある方、重症化の可能性が高いといわれる方々は、なるべく早めに医師に相談するようにしてください。 インフルエンザにかかった後の注意点<療養中>〔かかった人(本人)〕・安静にして休養をとる。・睡眠を十分にとる。・水分補給をしっかりとする。・周りに感染させないためにマスクを着用する。・人ごみなどへの外出を控える・学校や職場などは感染を拡大させる可能性があるため休むようにする。〔同居している方や看病をしている方〕・看護をしたあとは、手をこまめに洗う。・小さいお子さんが療養している場合は、大人がしっかりと見守るようにする。・持病がある方、妊娠している方は、可能な限りなるべく別の部屋で過ごす。<回復後> 熱が下がっても、インフルエンザの感染力は残っています。特に治療薬などにより急激な高熱が、すぐにすっと下がることがあります。完全に感染力がなくなる時期については個人差もあると言われていますが「体調は悪くないな」「もう治ったかな」「元気だし仕事に(学校に)行けるかな」と思っていても、まだまだ他の人に感染させるウイルスを体内に持っている可能性があります。 外出を控える日数などについては医師や医療機関にご相談ください。現在、学校保健安全法では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」を出席停止期間と定めています。 インフルエンザにかからないために(予防/感染防止) 基本的な感染対策 みなさんが2020年からCOVID-19として、しっかりと行ってきた3密(密集、密閉、緊密)を避けること、基本的な感染対策(飛沫感染対策、エアロゾル感染対策、接触感染対策)は、インフルエンザ対策に対してももちろん有効です。 感染が大きく拡大している場合には、リスク(通勤電車の中、人込みの中など)に応じて適切なマスクの着用をお勧めします。 マスク着用には2つの意味があります。まずは、自らへの感染リスクを下げるためです。この場合のマスクの着用が効果的な場面としては、 ・発熱や席をしている人のケアを行う時 ・医療機関を受診する時、見舞いに行く時 ・高齢者など重症化リスクの高い方を訪問する時 ・インフルエンザの流行期に混雑した場所に行く時もう一つは、自分が感染した場合に周辺へのウイルス拡散を防ぐためです。この場合としては、 ・発熱、倦怠感などの症状がある場合 ・鼻水、咳などの症状がある場合(この場合のマスク着用は「咳エチケット」の一環です。)「咳エチケット」とは…・咳・くしゃみが出る時は、他の人にうつさないためにマスクを着用しましょう。マスクを持っていない場合は、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて1m以上離れましょう。・鼻みず・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、 手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗いましょう。・咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。 予防接種 インフルエンザワクチンの予防接種には、発症をある程度抑える効果や、重症化を予防する効果があり、特に高齢者や基礎疾患のある方など、罹患すると重症化する可能性が高い方には効果が高いと考えられます。高齢者の方はインフレンザのあとに細菌性の肺炎を合併される方が多いですが、そのためには「肺炎球菌ワクチン」が有効です。65歳の方には定期接種となっていますので、ぜひ、こちらも注意してください。 さいごに 新型コロナウイルスの流行以来、2021年、2022年は流行がありませんでしたが、今年(2023年)に入り季節性インフルエンザの流行がみられました。 3月には一旦収束に向かいましたが、4月以降も患者数が確認され、例年なら流行していない6月~8月という夏の時期にも患者数の確認が続き、そして、9月に新学期を迎える学校などを中心に、さらに流行が拡大し、現在の流行に至っています。 流行のピークの予想は難しいですが、年末から年始にかけてピークになるのではないかと言われています。年末年始は人の移動も多く、家族、親族、友人・知人など様々な人と会う機会も多くなります。そんな時期とピークが重なります。正しい知識と適切な対策をもって、楽しい年末年始を迎えられるよう今回「インフルエンザ」というテーマを取り上げました。 参照URL・厚生労働省 令和5年度インフルエンザQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2023.html・国立感染研究所 インフルエンザとはhttps://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/219-about-flu.html・一般社団法人日本感染症学会提言 2022-2023年シーズンのインフルエンザ対策について(一般の方々へ)https://www.kansensho.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=46・一般社団法人日本感染症学会ガイドライン2023/24シーズンにおけるインフルエンザワクチン等の接種に関する考え方chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/influenza_vaccine_230925.pdf・一般社団法人日本呼吸器学会 呼吸器の病気 インフルエンザ https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/a/a-02.html・厚生労働省 インフルエンザの基礎知識chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/file/dl/File01.pdf・日本医師会 インフルエンザ総合対策https://www.med.or.jp/doctor/kansen/influenza/005423.html
記事を読む